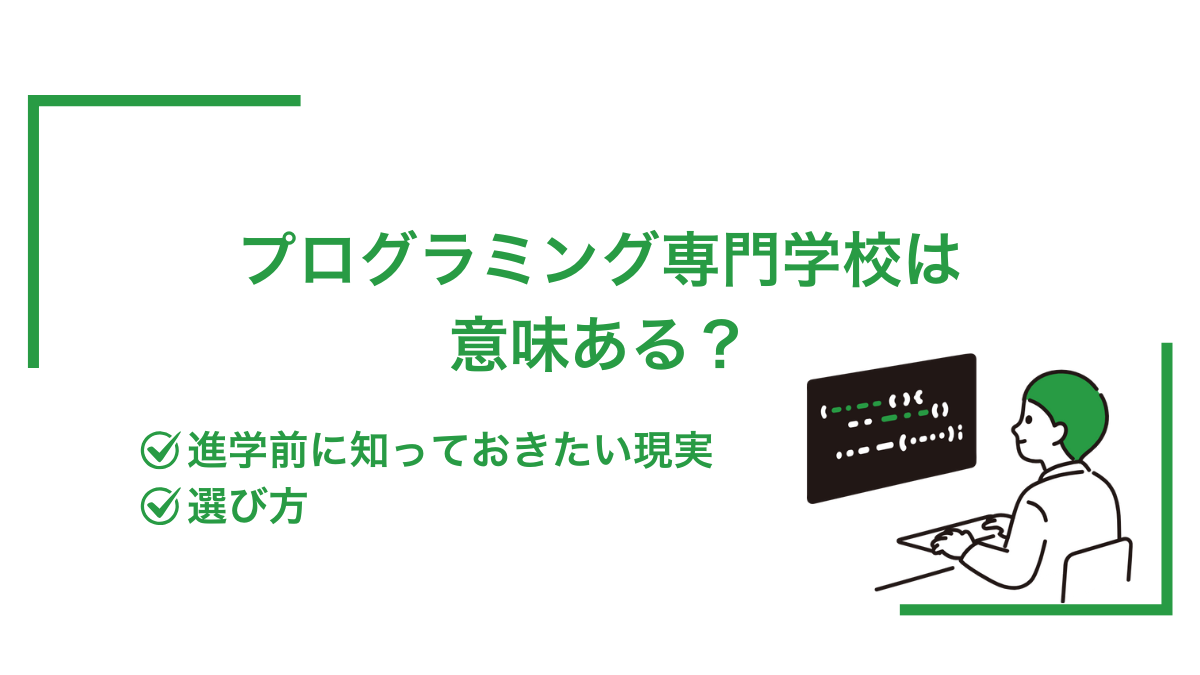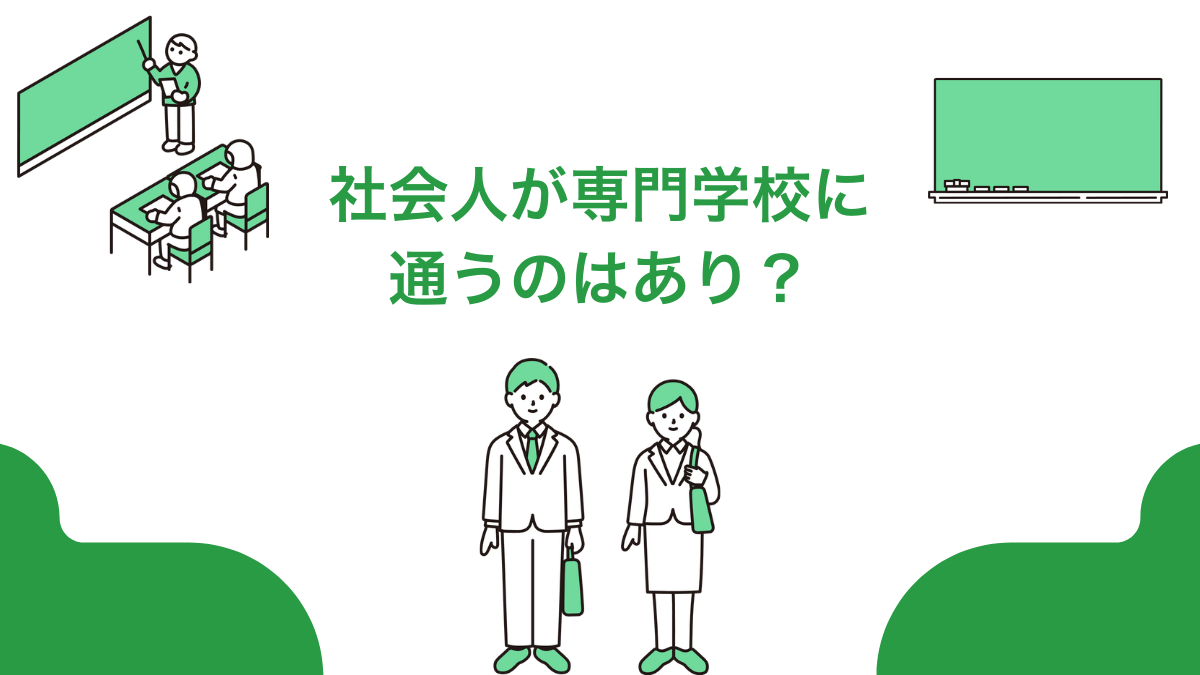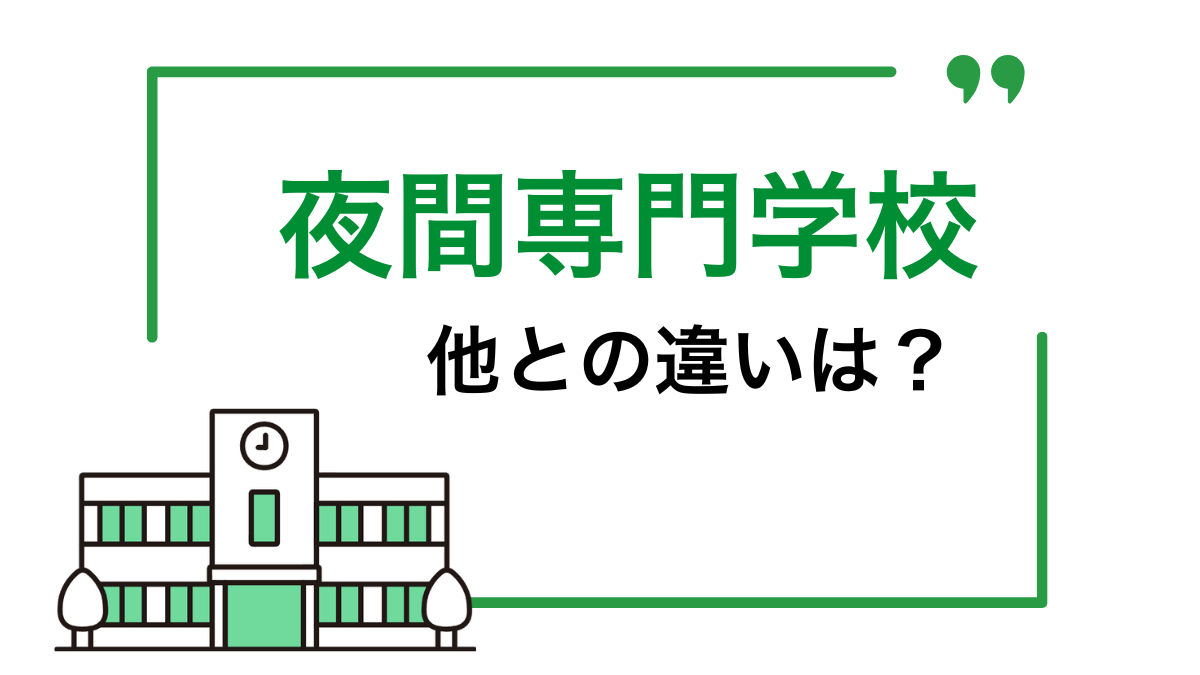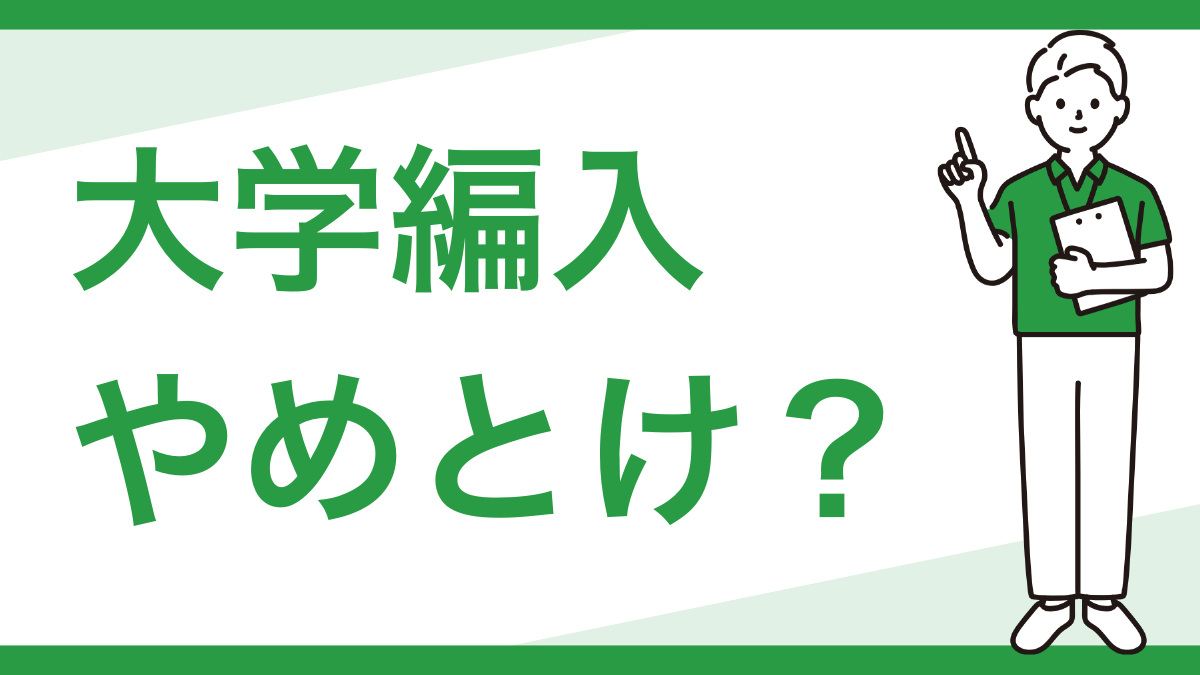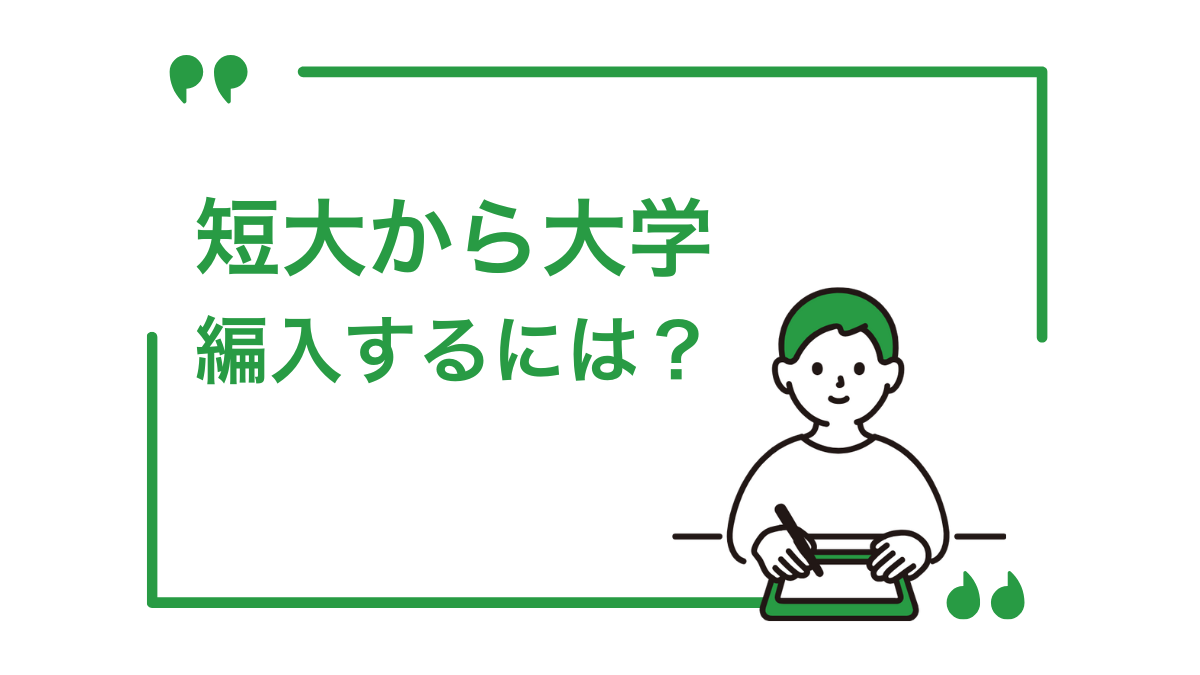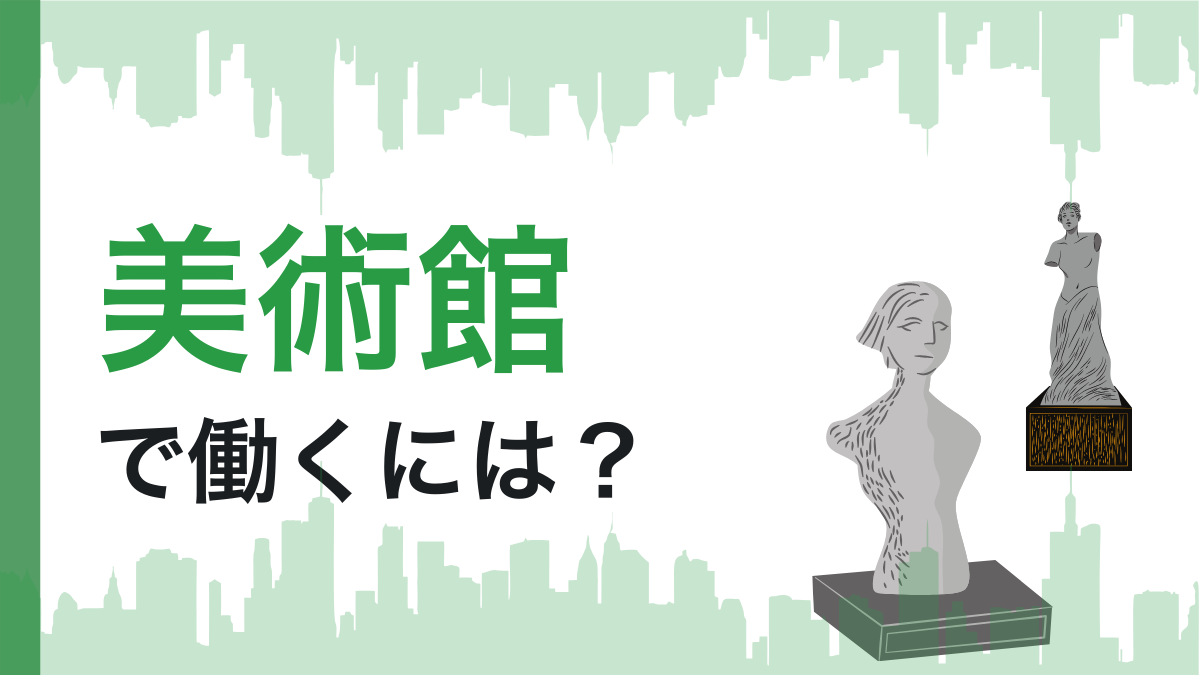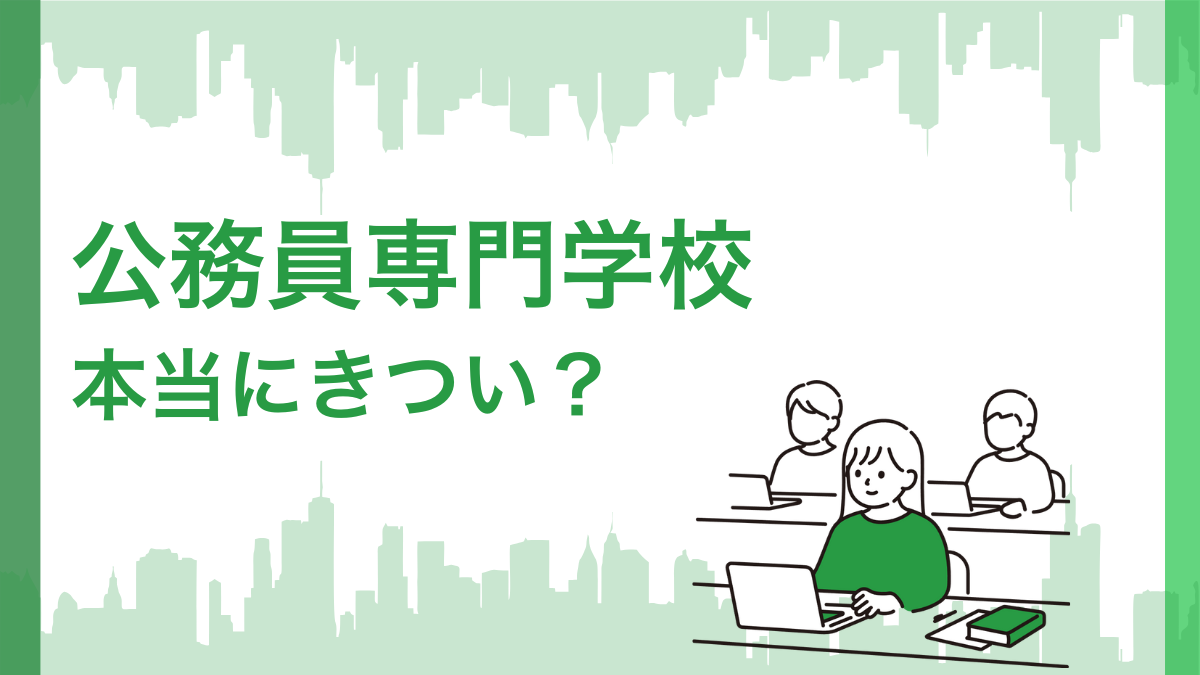将来性の高いIT業界で働きたいと考えたとき、「まずはプログラミングを学ぼう」と思う人は少なくありません。その中で選択肢の一つとなるのが「プログラミング専門学校」ですが、ネットで検索すると「意味ない」「無駄だった」という意見も目立ちます。
本記事では、なぜそうした声があるのかを客観的に分析しつつ、専門学校に通う意味や、後悔しない学校選びのポイントについて解説します。これから進路を検討する方にとって、現実を正しく理解するための材料としてご活用ください。
「プログラミング専門学校は意味ない」と言われる理由とは?
「意味ない」とされる理由には、実体験に基づく厳しい意見が少なくありません。ここでは、その代表的な声を根拠とともに整理していきます。
授業内容が独学と大差ない場合もある
多くの専門学校では、HTMLやCSS、JavaScriptといった基礎的な内容から授業がスタートします。しかし、こうした初歩的な内容は、無料の学習サイトやYouTubeでも学べるのが実情です。
特に、実務経験がある人や自主的に学ぶ意欲が高い人にとっては、「これなら自分で勉強したほうが早い」と感じてしまうケースもあります。学校によっては教材が古く、最新技術に触れられないまま卒業してしまうこともあり、「期待していたほどの価値が感じられなかった」という声につながります。
就職保証が実際には不透明なケースも
「就職率90%以上」と謳う専門学校も多いですが、その内訳を確認すると、業務委託や非正規、SES(客先常駐型)といった働き方が含まれている場合もあります。
見かけ上の数字が良くても、実際に安定したIT企業に正社員として就職できるかどうかは別問題です。就職支援の実態がブラックボックス化しており、サポートの質にばらつきがあることも、「意味がなかった」と感じる一因となっています。
高額な学費に対するリターンが見えづらい
専門学校の学費は年間で100万円を超えることも珍しくなく、2年間通えば200万円以上の投資になります。にもかかわらず、卒業後の就職先が非正規やSESであれば、給与面で十分なリターンが得られないことも。
このように「費用対効果」の観点から不満を抱く人は少なくありません。特に、教育ローンや奨学金を使って通う場合、返済負担と将来のキャリアにギャップが生まれやすくなります。
カリキュラムの古さ・現場とのギャップ
IT業界は技術の移り変わりが激しく、1年経つだけでも使われる言語やフレームワークが変わることもあります。しかし、専門学校では一度策定されたカリキュラムが数年間更新されないこともあり、現場のニーズとズレているケースが見られます。
たとえば、現在主流のReactやTypeScriptを学ばずに卒業するカリキュラムも存在し、現場で求められる即戦力とは言えない人材になってしまう可能性があります。
専門学校のメリットと価値を正しく理解する
「意味ない」という意見ばかりが目立つ一方で、専門学校の教育が全く無価値かというと、そうとは限りません。適切に選び、活用できれば大きなメリットもあります。
基礎から体系的に学べる環境が整っている
独学では学びが偏りがちになりやすいですが、専門学校ではカリキュラムが体系的に整備されています。段階的に理解を深めていけるため、未経験者にとっては安心して学習を進めやすい環境です。
また、演習や課題提出などのアウトプットの機会も設けられており、理解の定着につながります。
現役エンジニアによる指導が受けられることも
学校によっては、現役のエンジニアや業界経験者が講師を務めているケースもあります。現場のリアルな知識や最新の技術トレンドを学べる点は、独学では得にくい強みです。
質問があった際にすぐ回答をもらえる環境も、理解のスピードを加速させる一因になります。
仲間と切磋琢磨できるコミュニティの存在
モチベーションの維持においては、学習仲間の存在が非常に重要です。専門学校では、同じ目標を持つ仲間と共に学ぶことで、競争意識や連帯感が生まれやすくなります。
グループワークやチーム開発を通して、実際の現場に近い環境を経験できることもあり、協調性やコミュニケーション能力の向上にもつながります。
ポートフォリオや就職支援制度の活用可能性
専門学校の中には、卒業制作で本格的なポートフォリオを作成する課題がある場合もあり、就職活動においては大きな武器になります。
さらに、求人紹介や履歴書の添削、模擬面接といったサポートが受けられる点も、特に就職活動が初めての人にとっては心強い存在です。
プログラミングを学ぶ他の手段との比較
プログラミングを学ぶ手段は専門学校だけではありません。他の選択肢と比較することで、自分に合った学び方を見極めやすくなります。
独学:コストは低いがモチベーションの維持が課題
書籍や無料サイト、動画コンテンツを使った独学は、ほとんどコストがかからない点が魅力です。自分のペースで進められる自由さもあります。
ただし、習慣化や継続が難しく、エラー時に挫折してしまうケースが多いのも事実です。体系立てた学習や、フィードバックの機会が少ないことも難点です。
オンラインスクール:柔軟な学習スタイルだがサポートに差
プログラミングスクールは近年人気が高まっており、動画教材やチャットでの質問対応など、学びやすい環境が整っています。
ただし、スクールによっては講師の質や対応の速さにばらつきがあり、自分に合ったサービスを選ぶ必要があります。料金体系も月額制から一括支払いまで多様で、比較検討が必須です。
大学:より学術的だが時間と費用がかかる
情報系の学部では、アルゴリズムや数学的な基礎などを含め、より学問的な知識を学ぶことができます。長期的にIT業界で活躍したい人や研究職を目指す人には適しています。
一方、学費や学習期間の長さから、すぐに就職を目指す人には不向きな場合もあります。
専門学校:短期集中で実践的だが選び方に注意が必要
専門学校は、2年間で実践的なスキルを集中して学べるのが特徴です。即戦力としての就職を目指す人にとっては効率的な選択肢とも言えます。
ただし、前述の通り学校によって教育内容に大きな差があり、慎重な選択が必要です。
意味のある専門学校を選ぶためのチェックポイント
後悔しない進路選びのためには、学校選びの段階で多角的に情報を集める必要があります。
カリキュラムが最新技術に対応しているか
技術の陳腐化が早いIT業界では、最新技術を扱うカリキュラムかどうかが重要な評価基準です。ReactやTypeScript、クラウドサービスなど、現場で使われる技術が含まれているかを確認しましょう。
教員の実務経験と指導力を確認する
講師のプロフィールを確認し、どのような経歴を持ち、どんな現場で働いてきたかを調べることは大切です。現役エンジニアが教えているかどうか、また質問対応の仕組みもチェックしておきたいポイントです。
就職実績やサポート体制の透明性
就職率だけではなく、どんな企業に就職しているのか、卒業生の声なども確認しましょう。また、履歴書添削や企業紹介、キャリア相談などの支援がどの程度受けられるのかも重要です。
体験授業や資料請求で事前調査をする
公式サイトだけでは分からない情報も多いため、オープンキャンパスや体験授業に参加して実際の雰囲気を確認するのがおすすめです。資料請求や個別相談で疑問点を解消することも忘れずに行いましょう。
「意味ない」と感じさせないために必要なマインドセット
学習の成果は、環境だけでなく本人の意識や取り組み方にも大きく左右されます。学校選びと同様に、心構えも成功のカギとなります。
目的意識を持って通うことの重要性
「とりあえず進学する」という姿勢では、学びの成果は薄くなってしまいます。自分が将来どんなエンジニアになりたいのか、なぜ専門学校を選ぶのかという目的意識を持つことで、日々の学習にも集中力が生まれます。
受け身ではなく主体的に学ぶ姿勢
授業をただ受けるだけでは、実践力は身につきません。わからないところを積極的に質問し、さらに自分で学びを深める姿勢が求められます。
卒業後のキャリアビジョンを描くこと
どのような職種・業界で働きたいかを明確にすることで、必要なスキルも逆算しやすくなります。単に「就職すること」だけをゴールにせず、長期的なキャリア設計を意識することが大切です。
学外のリソースも積極的に活用する
プログラミングは常にアップデートされる分野です。学校以外の教材や勉強会、オンラインコミュニティなども積極的に活用し、自主的に知識を広げる努力が求められます。
まとめ
「プログラミング専門学校は意味ない」と言われる背景には、授業内容や就職支援の質に対する不満、費用対効果への疑問が存在します。しかし、すべての専門学校が無価値なわけではなく、正しく選び、自分の目的を持って通えば、十分に価値のある学びの場になります。
大切なのは、「どこで学ぶか」以上に「なぜ学ぶのか」「どのように学ぶのか」を明確にすることです。焦らず冷静に、情報収集と自己分析を行い、自分にとって本当に意味のある選択をしていきましょう。
関連のInstagram投稿はこちら
Instagramでは、専門学生に役立つ情報を日々発信中!
興味がある人は是非いいねとフォローをお願いします!