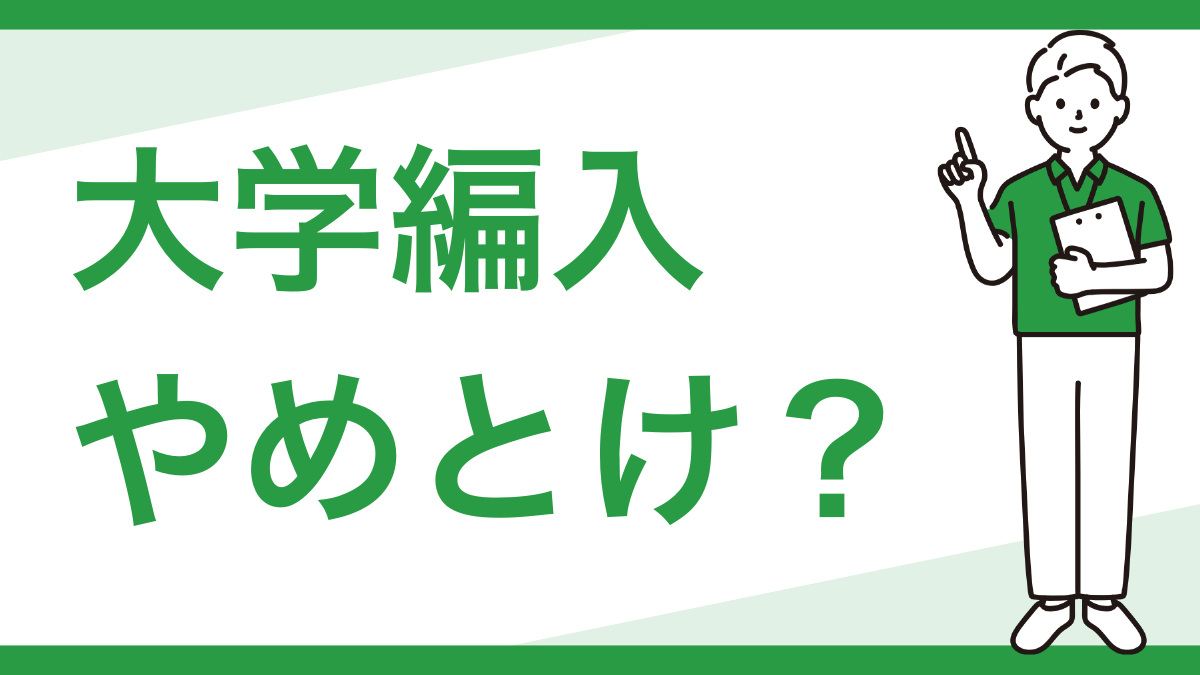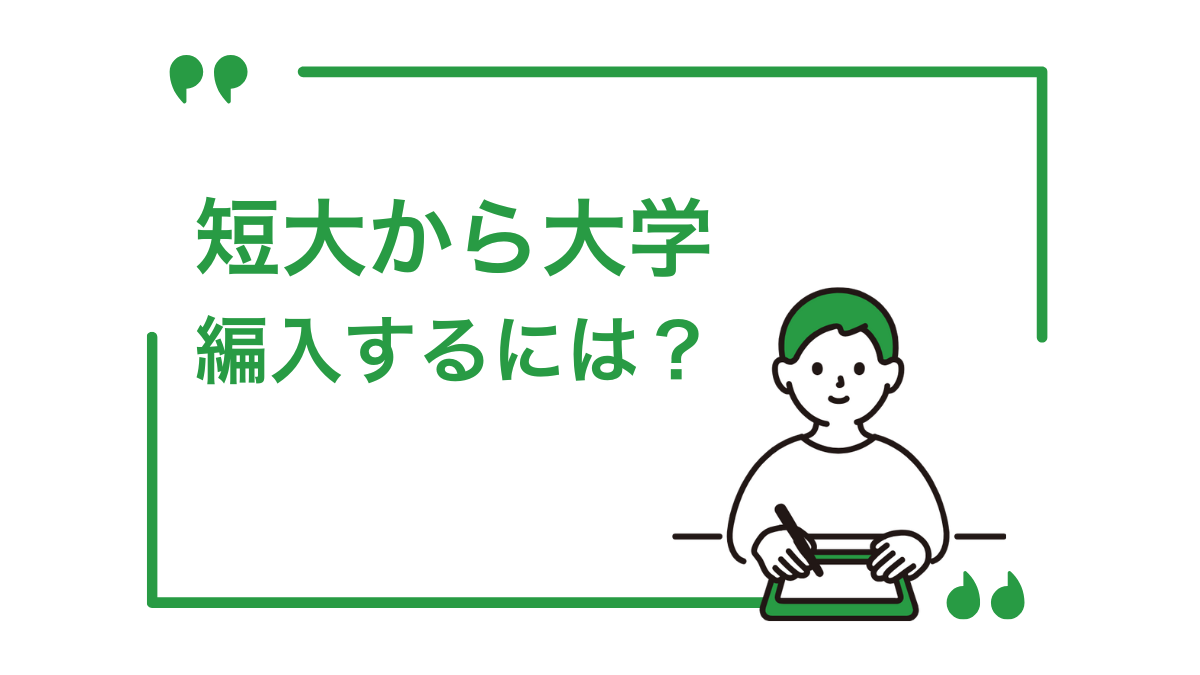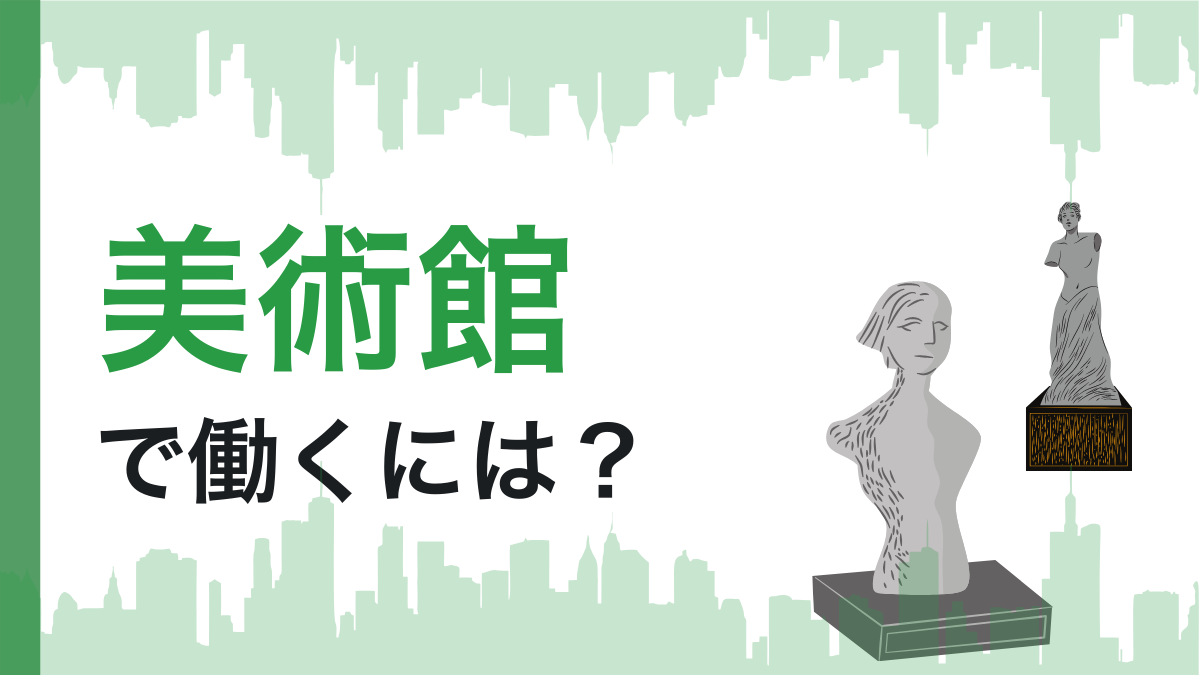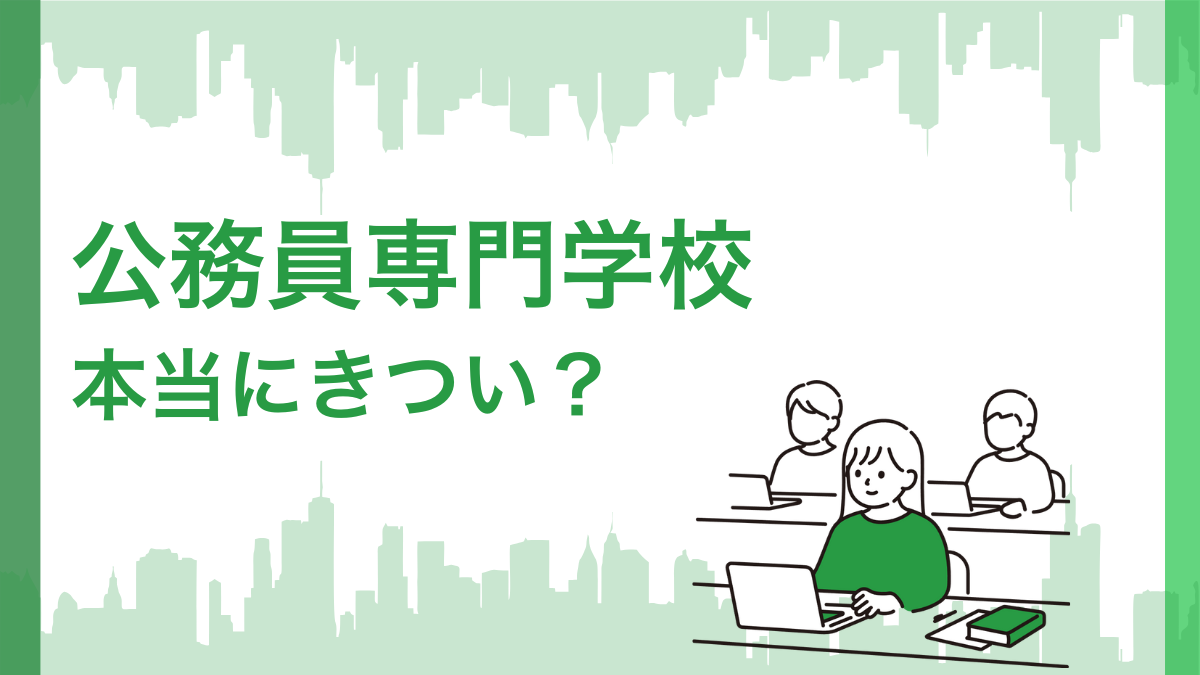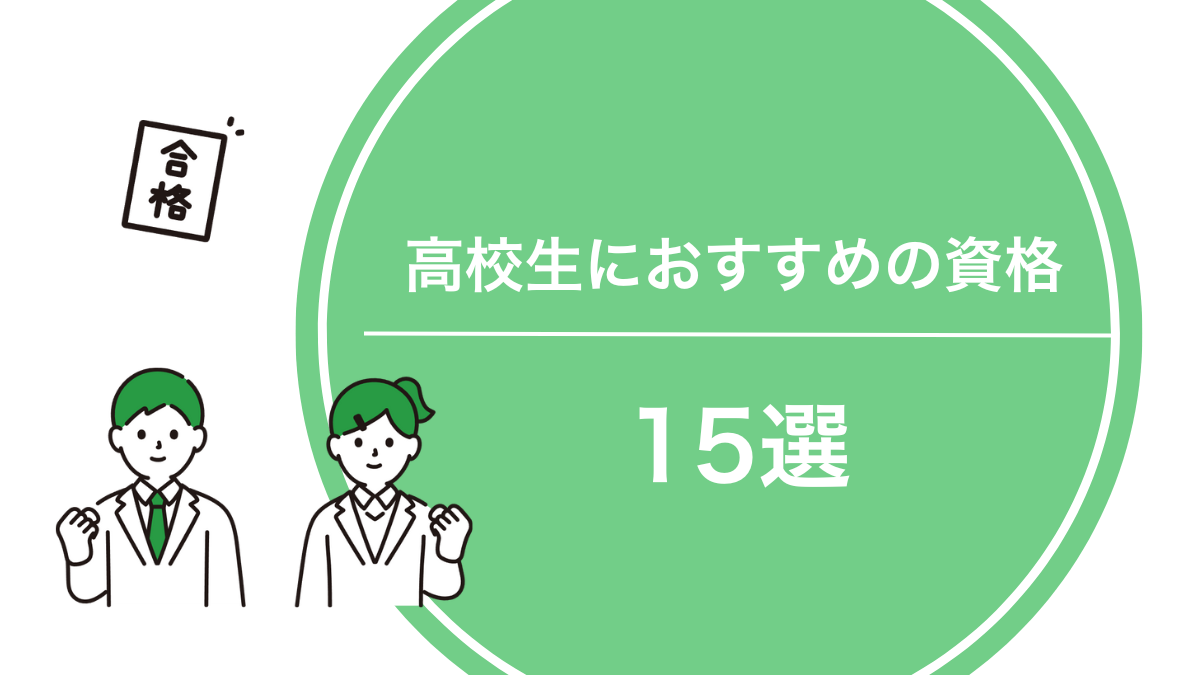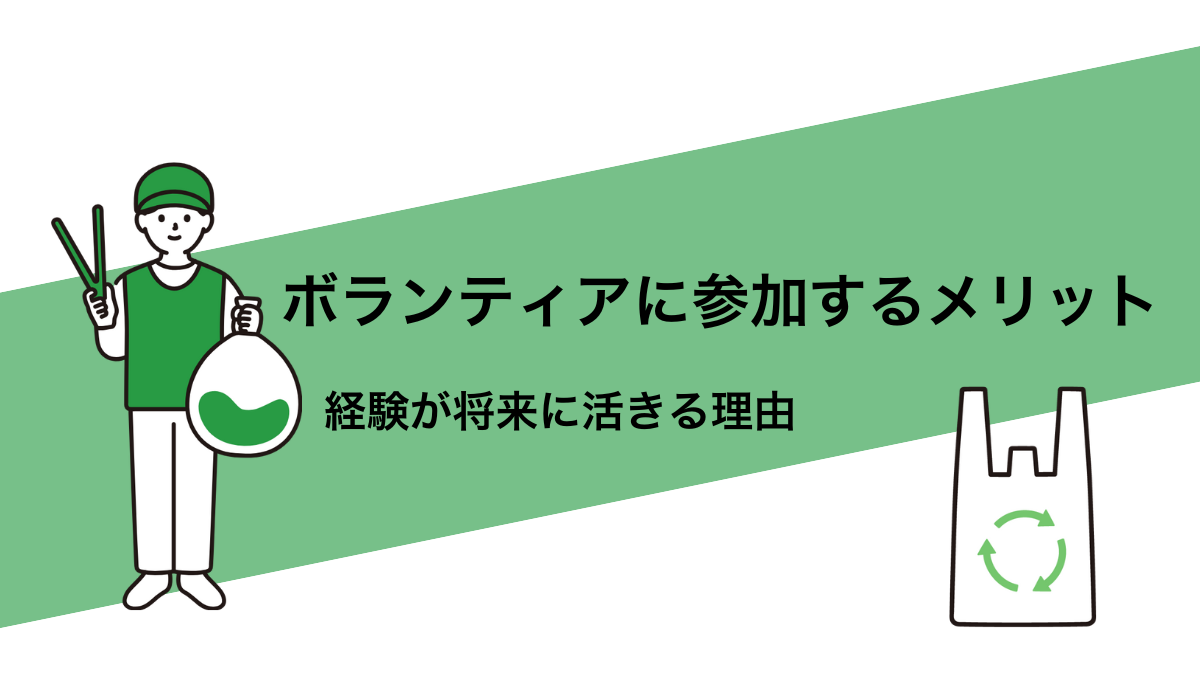大学在学中や短大・専門学校に通う中で、「やっぱり別の大学で学びたい」「学士号を取りたい」と考えて大学編入を検討する人は少なくありません。
しかしネット上では「大学編入はやめとけ」という意見もよく見られます。なぜそのように言われるのでしょうか。
この記事では、大学編入が「やめとけ」と言われる理由を整理しつつ、編入のメリットや向いている人の特徴、成功に向けた準備方法を解説します。
大学編入がやめとけと言われる理由とは
大学編入が「やめとけ」と言われる理由は以下のとおりです。
【大学編入がやめとけと言われる理由】
- 必ず編入できるとは限らないため
- お金がかかるため
- 編入後の大学生活が大変なため
順に解説します。
必ず編入できるとは限らないため
編入試験は受験者数に比べて募集枠が少なく、倍率が高くなるケースが多いです。
過去問や情報が限られているため対策も難しく、「合格できる保証がない」という点でリスクが大きいと感じる人もいます。
お金がかかるため
編入するには入学金や授業料などの学費が新たに必要です。
短大や他大学で既に費用を払っているため、通算すると教育費の負担が重くなるケースもあります。さらに通学環境が変われば、引っ越しや生活費の追加負担も考慮しなければなりません。
編入後の大学生活が大変なため
編入生は3年次からの合流が多いため、カリキュラムやゼミに一気に適応する必要があります。既にグループができあがっている中に途中参加する形になるため、人間関係の構築も簡単ではありません。
また、単位認定の違いから卒業に必要な科目が想定以上に多くなり、学習負担が増えることもあります。
大学編入のメリット
一方で、大学編入には「やめとけ」と言われる声に反して魅力的なメリットも存在します。代表的なものは以下のとおりです。
【大学編入のメリット】
- 興味のある学問が学べる
- 交友関係の幅が広がる
順に解説します。
興味のある学問が学べる
最初に進学した学部で「自分のやりたいことと違った」と感じた場合でも、編入を通じて改めて興味のある分野を学ぶことができます。
学士号を取得しつつ専門性を深め直せるのは大きなメリットです。
交友関係の幅が広がる
新しい大学に進むことで、これまで出会えなかった仲間や教授とのつながりが生まれます。
異なる環境に飛び込むことで新しい視野を得られる点も、編入ならではの魅力といえるでしょう。
大学編入に向いている人・向いてない人
大学編入に「向いている人」と「向いていない人」を整理すると以下のようになります。
【向いている人】
- 明確な目的や学びたい分野がある人
- 自主的に学習を進められる人
- 新しい環境に飛び込む柔軟性がある人
【向いていない人】
- ただ「学歴を上げたい」という理由だけで考えている人
- 学習意欲が低く、試験対策や自己管理が苦手な人
- 新しい人間関係の構築が負担に感じる人
大学編入を目指す場合のポイント
大学編入を検討する場合は、次のような準備が必要です。
【大学編入するために必要な準備】
- 志望理由や学修計画を明確にする
- 英語や小論文などの試験対策を早めに始める
- 過去問や募集要項を調べて出題傾向を把握する
特に「なぜその大学で学びたいのか」を具体的に説明できることは合格の鍵になります。
編入する大学の選び方
編入先を選ぶ際は、ネームバリューだけではなく以下の点を意識しましょう。
【編入する大学の選び方】
- 学部・学科のカリキュラムが自分の学びたい内容と一致しているか
- 卒業後の進路実績が自分の目標に合っているか
- 編入生の受け入れ実績やサポート体制が整っているか
情報収集を怠らず、自分にとって最適な大学を選ぶことが成功への近道です。
まとめ
大学編入は「やめとけ」と言われるように、合格の保証がないことや費用負担、編入後の大変さといったリスクがあります。しかしその一方で、興味のある学問を学び直せる、交友関係を広げられるといった大きなメリットもあります。
結局のところ重要なのは、自分がどんな目的で大学編入を考えているのかです。目的が明確で、しっかり準備できる人にとっては大きなチャンスとなります。将来像を描いたうえで、編入するかどうかを冷静に判断しましょう。