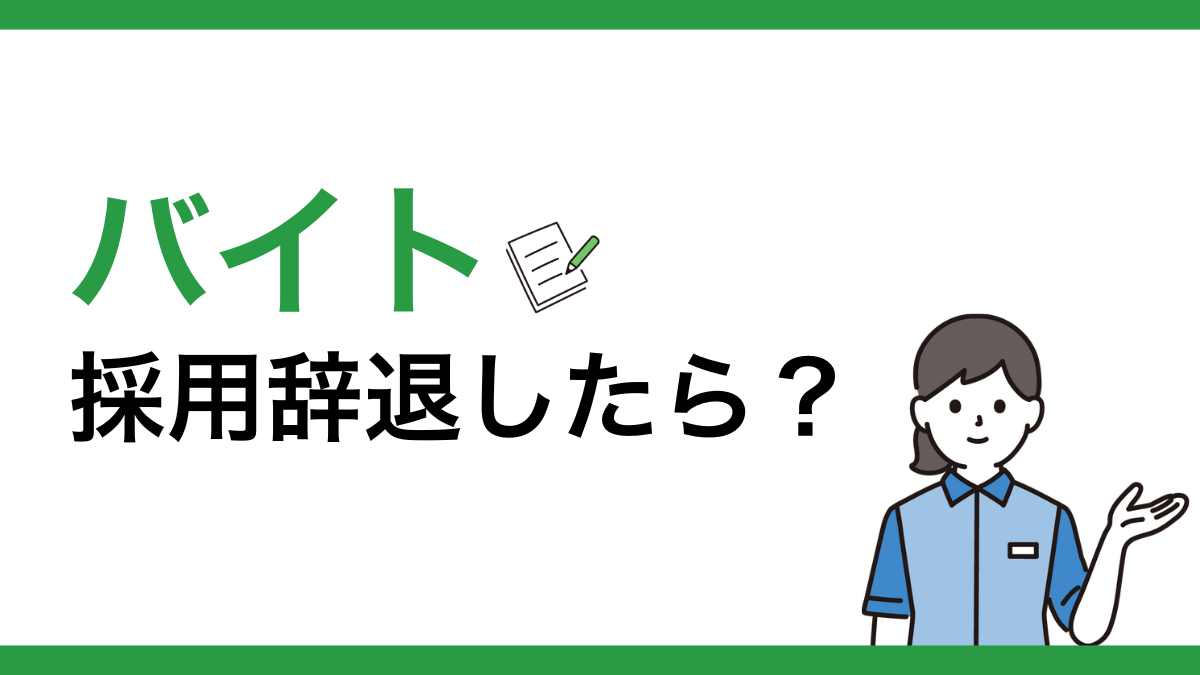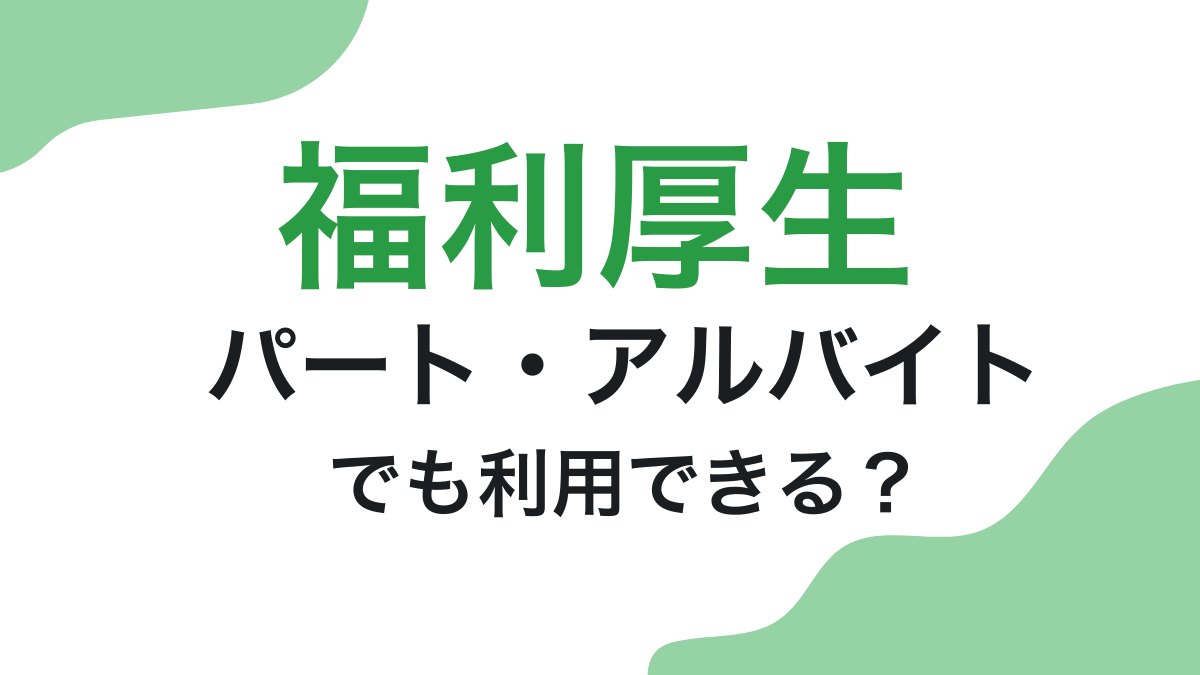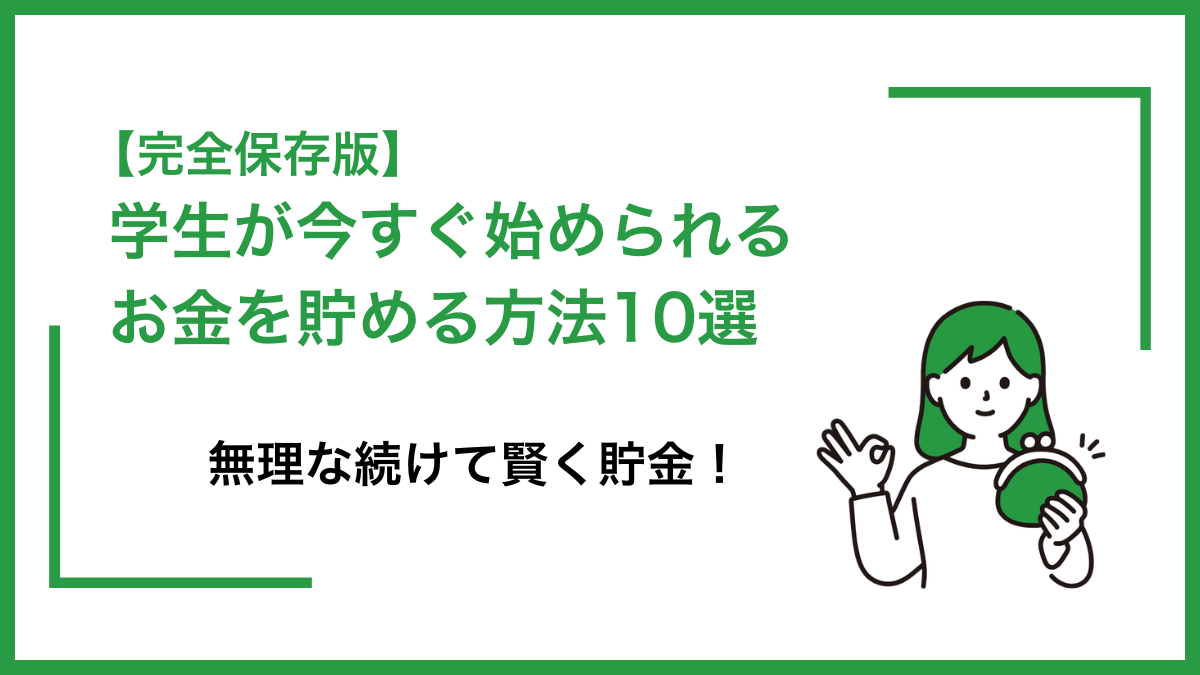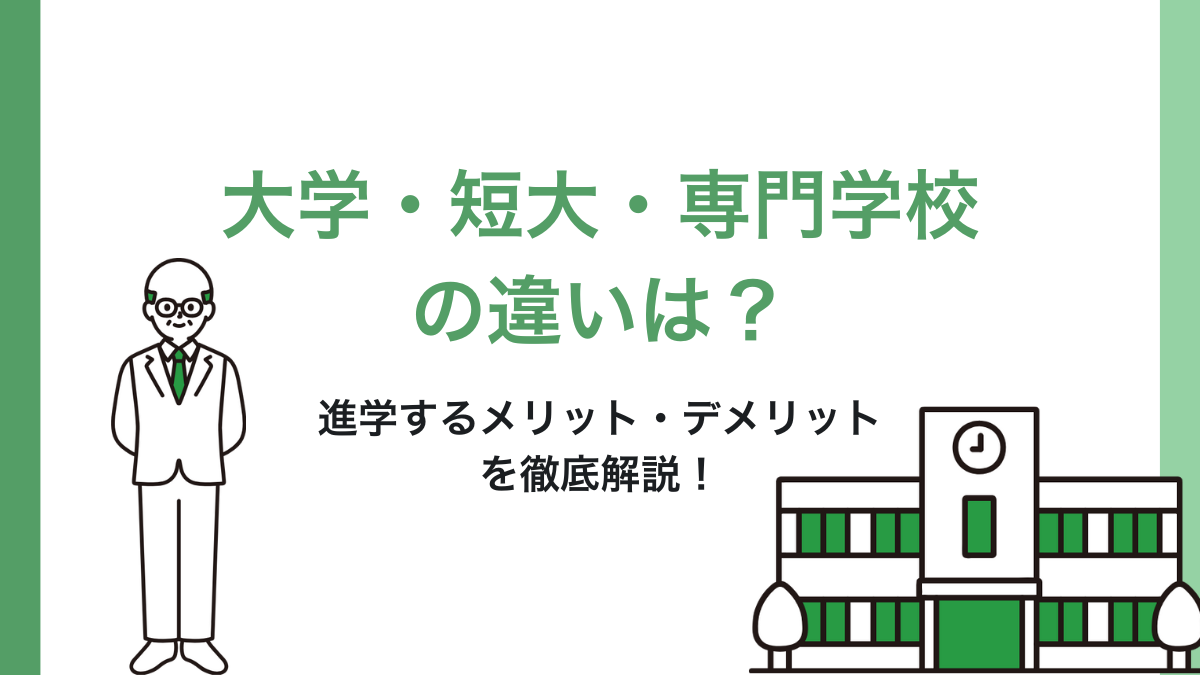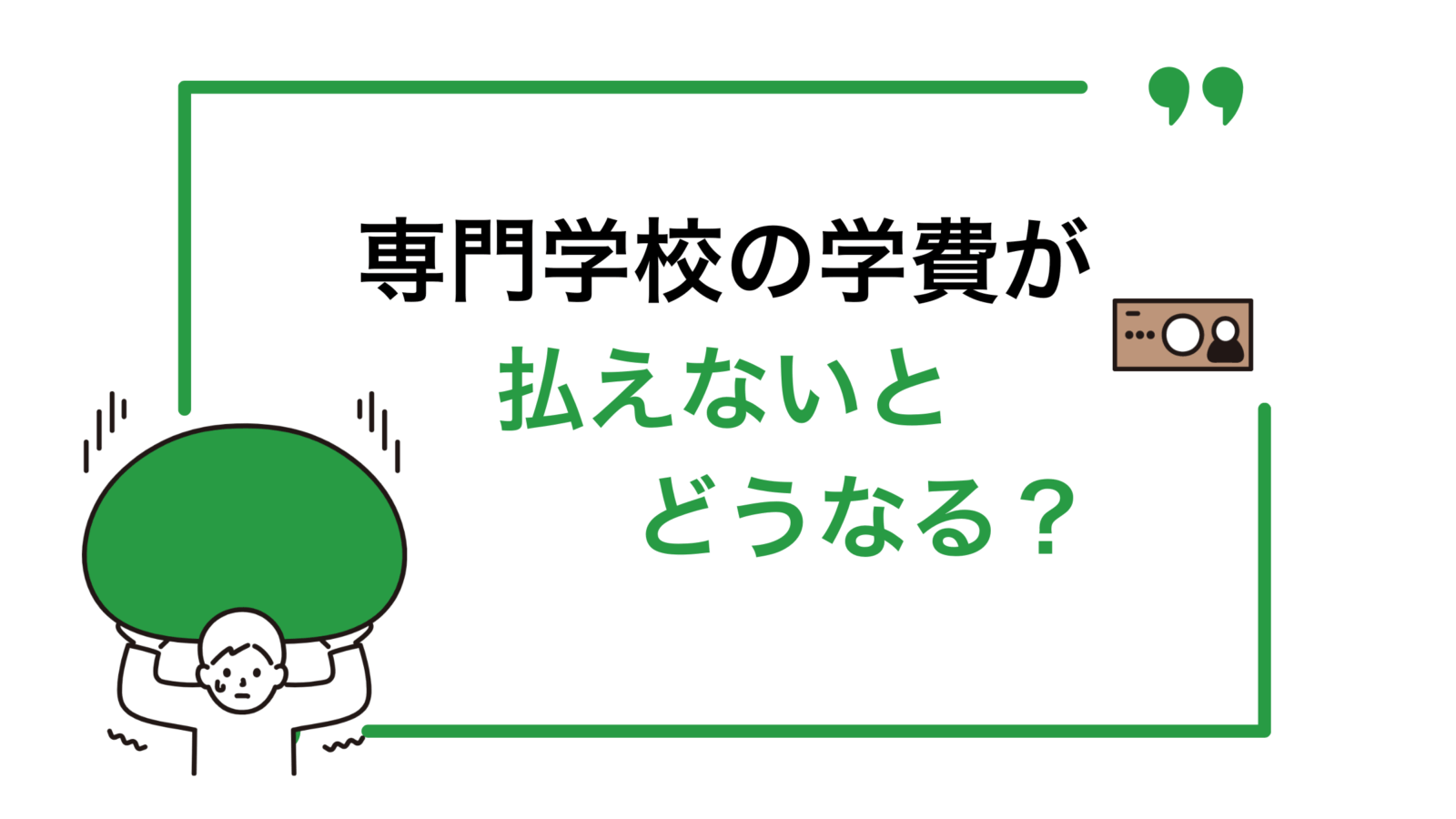奨学金を利用する学生にとって、保証人の選定は重要なプロセスの一つです。
なかでも、祖父母を保証人にするケースもありますが、65歳以上の祖父母は原則として奨学金の保証人には選べないことが一般的です。
この記事では、奨学金保証人の条件や65歳以上の祖父母が保証人になれない理由、保証人を依頼できない場合の対処法について解説します。
65歳以上の祖父母は奨学金の保証人対象外となる可能性

奨学金の保証人制度には、連帯保証人と保証人の2種類があり、どちらも一定の条件を満たす必要があります。
65歳以上の祖父母は、基本的にこの保証人の条件を満たさないことが一般的で、基本的に保証人には選ばれません。
保証人は、奨学生が返還できなくなった際に代わりに返済する責任を負うため、年齢制限が設けられています。65歳以上の祖父母を保証人に選びたい場合、通常の手続きに加えて「返還保証書」や資産状況を証明する書類が必要です。しかし、これらの書類があっても、保証人として認められるかどうかは審査によって決まります。
奨学金の保証人の条件
奨学金の保証人には、連帯保証人と保証人が存在し、それぞれ異なる条件があります。保証人として選任されるためには、次の条件を満たす必要があります。
【奨学金の保証人の条件】
- 奨学生本人および連帯保証人と別生計であること。
- 奨学生本人の父母を除く、おじおば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- 返還誓約書に印字の誓約日時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合、その届出日現在で65歳未満であること。
- 返還誓約書に印字の誓約日時点で未成年者でないこと。
- 学生でないこと。
- 奨学生本人または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- 債務整理中(破産等)でないこと。
- 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
※保証人の2,3については「返還保証書」および資産等に関する証明書の提出を条件に、貸与予定総額の2分の1以上の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者(年間収入金額、資産等の状況が以下の表のいずれかの基準を満たす者)に代えることができます。
保証人の候補となる人が年齢制限を超えている場合や適切な親族がいない場合は、代わりの方法が必要となるため、予め対策を考えておくことが重要です。
奨学金の連帯保証人の条件
連帯保証人は、奨学生が返済できない場合にその義務を引き継ぐため、保証人よりも厳しい条件が課せられます。
【奨学金の連帯保証人の条件】
- 奨学生本人が未成年者の場合、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
- 奨学生本人が成年者の場合、その父母。父母がいない等の場合、奨学生本人のおじおば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- 返還誓約書に印字の誓約日時点で未成年者でないこと。
- 学生でないこと。
- 奨学生本人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- 債務整理中(破産等)でないこと。
- 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
※連帯保証人の2については貸与予定総額の返還を条件に、貸与予定総額の2分の1以上の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者(年間収入金額、資産等の状況が以下の表のいずれかの基準を満たす者)に代えることができます。
保証人とは異なり、連帯保証人には分別の利益や検索の抗弁権、催告の抗弁権が認められず、奨学生本人と同等の責任を負うため、選任の際には慎重な検討が必要です。
奨学金の保証人を依頼できない場合の対処法

個々人の事情によっては、奨学金の保証人を選定できない場合もあるでしょう。
奨学金の保証人を依頼できない場合は以下の対処法を参考にしてください。
【奨学金の保証人を依頼できない場合の対処法】
- 返還保証書や資産等に関する証明書を用意して申し込む
- 機関保証を利用する
順に解説していきます。
返還保証書や資産等に関する証明書を用意して申し込む
保証人を依頼できない場合、通常の保証人選定に加えて返還保証書や資産等に関する証明書を用意することで、保証人として認められるケースがあります。65歳以上の祖父母を保証人にしたい場合、この書類は必須となります。
返還保証書には、奨学金の返済義務を負う意思があることを明記し、それを証明するための収入や資産状況を証明する書類の添付が必要です。資産状況を証明する書類としては預貯金残高証明書や固定資産評価証明書などが必要とされることが多いです。
これらの書類を適切に揃えることで保証人として認められる可能性が高まりますが、最終的な判断は奨学金の審査に委ねられます。
機関保証を利用する
奨学金の保証人が見つからない場合、機関保証を利用することも有効です。機関保証制度では、指定された保証機関が保証を引き受け、奨学生が返済を滞納した場合には保証機関が代わりに返済を行います。
その後、保証機関は奨学生に対して支払った金額を請求するため、実質的に保証機関が連帯保証人の役割を果たします。
機関保証を利用する際には、一定の保証料が発生しますが、保証人を個人で探す手間が省け、また、親族の年齢や経済状況に関わらず利用できる点が大きなメリットです。
特に、65歳以上の祖父母が保証人として認められない場合や、適切な親族がいない場合には、この制度の利用を検討する価値があるでしょう。
まとめ
本記事では、65歳以上の奨学金の保証人可否や依頼できない場合の対処法などを解説しました。
奨学金の保証人を選ぶ際には、年齢や親族関係、経済状況などの条件を慎重に確認する必要があります。65歳以上の祖父母は基本的に保証人として選べませんが、返還保証書や機関保証を利用することで、代替手段を取ることが可能です。
自身の状況に合わせた制度を利用し、スムーズに奨学金を利用できるようにしましょう。
関連のInstagram投稿はこちら
Instagramでは、専門学生に役立つ情報を日々発信中!
興味がある人は是非いいねとフォローをお願いします!