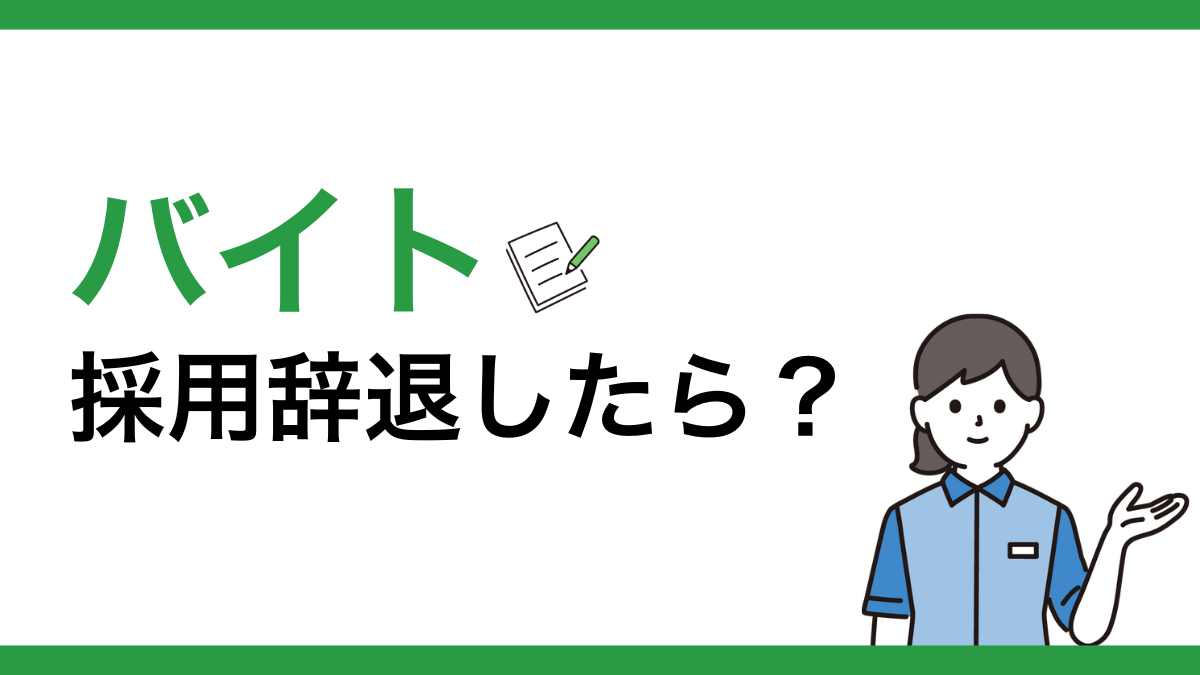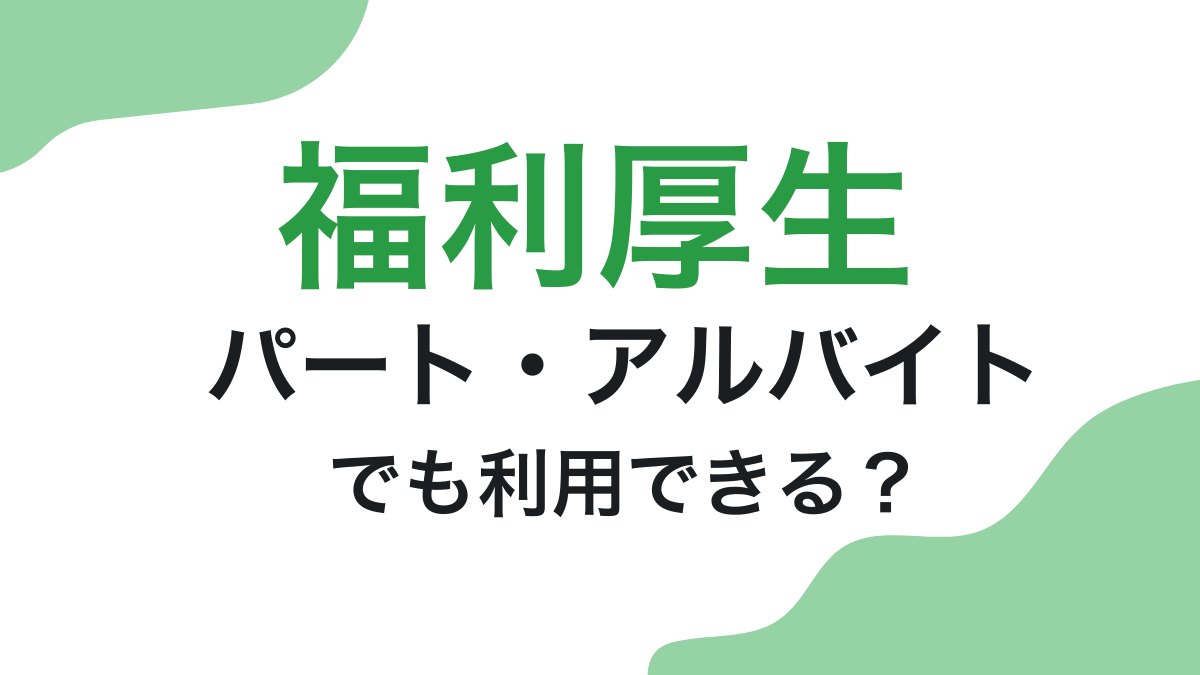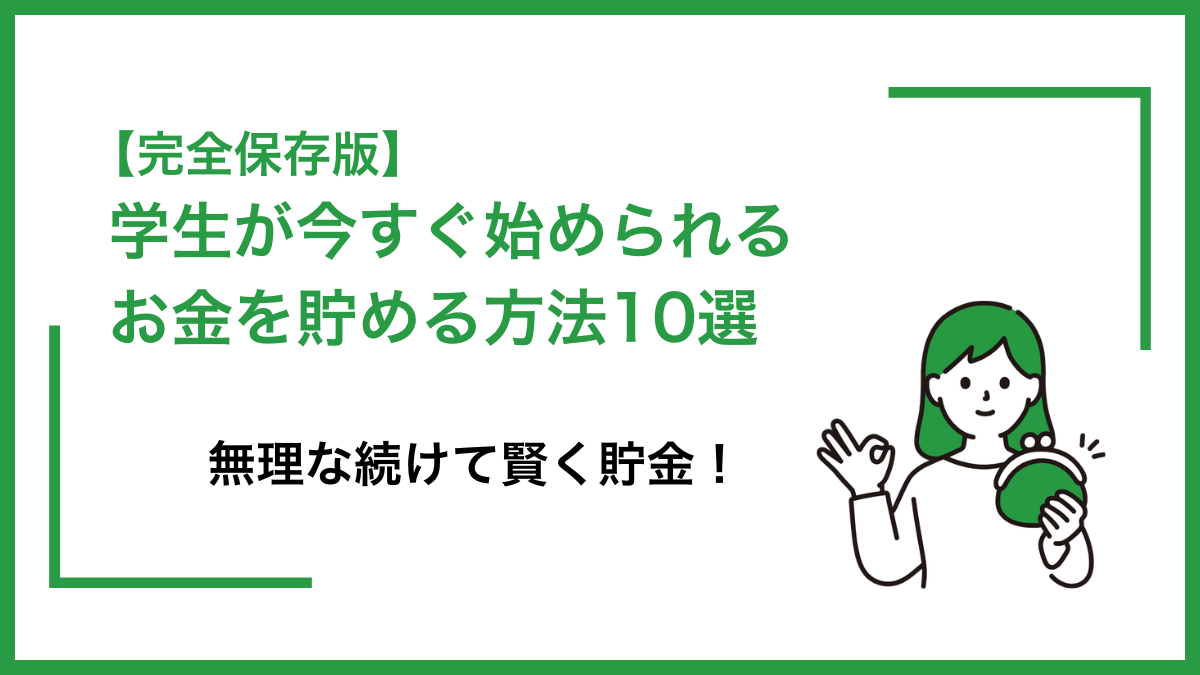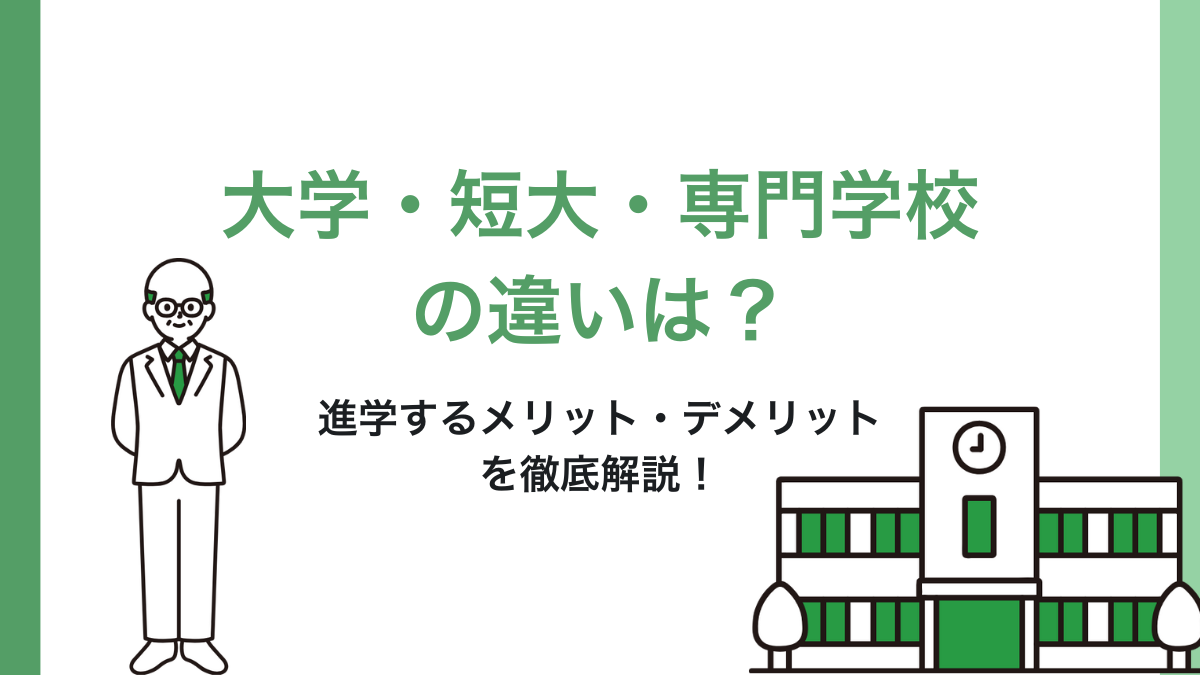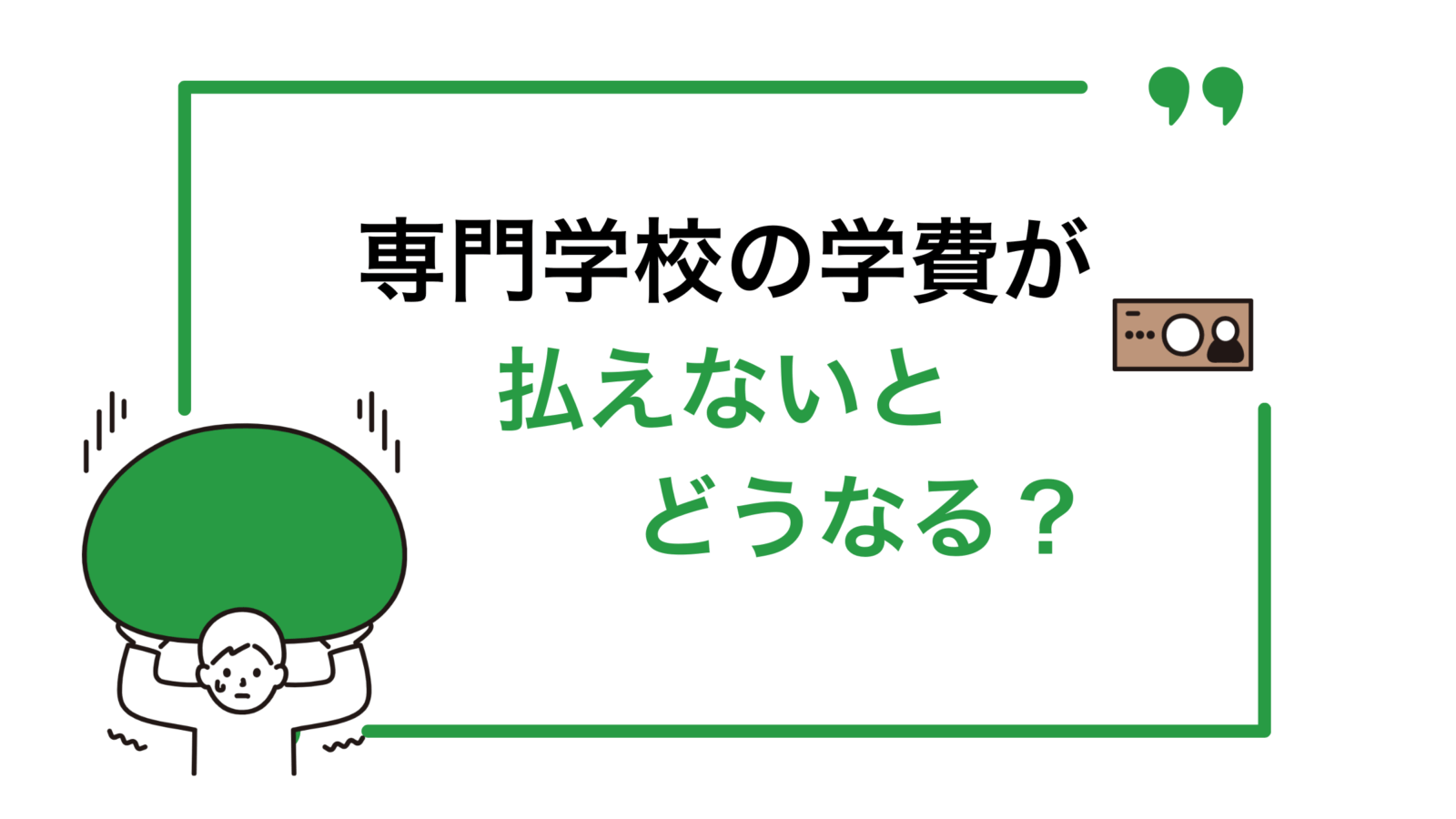奨学金の利用を検討するにあたって、人的保証制度を選択する場合、保証人の選定が必要です。しかし、奨学金の保証人に選ぶことができる人には条件があります。
この記事では、奨学金の保証人の条件や、保証人がいない場合の代替手段について詳しく解説します。特に「奨学金の保証人になれない人」に焦点を当て、どのような選択肢があるのかについて紹介していきます。
学生や保護者がスムーズに奨学金を利用できるよう、保証制度の重要なポイントを確認していきましょう。
奨学金の人的保証とは

奨学金の人的保証とは、奨学金の貸与を受けるにあたって、奨学生(返還者)の父母・親戚等に連帯保証人と保証人を引き受けてもらう制度です。
この制度は、日本学生支援機構を通じて提供され、連帯保証人と保証人の2種類があります。
奨学金の保証人の種類

人的保証では、保証人・連帯保証人を選任する必要があります。
以下では保証人・連帯保証人それぞれの概要を解説していきます。
保証人
奨学金の保証人は、奨学生本人と連帯保証人が返済できなくなった場合、奨学生に代わって返済を行う人物を指します。
保証人には分別の利益や検索の抗弁権、催告の抗弁権が認められており、連帯保証人に比べると負担は軽いものの、大きな責任を伴います。
連帯保証人
連帯保証人は、奨学生が奨学金の返済を延滞した場合、本人に代わって全額返済を行う義務を負う人物です。
通常、連帯保証人には奨学生の両親が選ばれることが一般的ですが、両親がいない場合や条件を満たさない場合は、兄弟姉妹や親戚が選ばれることがあります。
連帯保証人は、分別の利益や検索の抗弁権、催告の抗弁権が認められておらず、奨学生と同等の返済責任を負うため、奨学金の未済額全額を返済する義務があります。
さらに、連帯保証人には収入や資産の証明が必要であり、安定した収入がない場合や、年齢制限を超える場合は連帯保証人になれないことがあります。
奨学金の保証人の条件|なれない人はどんな人?

ここまで保証人と連帯保証人の概要を解説しましたが、実際にどんな人が保証人・連帯保証人になれるのでしょうか。
以下では奨学金の保証人・連帯保証人の条件について解説します。
保証人の条件
保証人は連帯保証人と比較すると責任は軽いものの、選定には以下の条件があります。
【奨学金の保証人の条件】
- 奨学生本人および連帯保証人と別生計であること。
- 奨学生本人の父母を除く、おじおば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- 返還誓約書に印字の誓約日時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合、その届出日現在で65歳未満であること。
- 返還誓約書に印字の誓約日時点で未成年者でないこと。
- 学生でないこと。
- 奨学生本人または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- 債務整理中(破産等)でないこと。
- 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
※保証人の2,3については「返還保証書」および資産等に関する証明書の提出を条件に、貸与予定総額の2分の1以上の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者(年間収入金額、資産等の状況が以下の表のいずれかの基準を満たす者)に代えることができます。
保証人は原則として4親等以内の親族が条件です。4親等というのは、両親が1親等・兄弟姉妹が2親等・叔父叔母が3親等・従兄弟が4親等となります。
連帯保証人の条件
連帯保証人は奨学生と同等の責任を持つため、厳しい条件があります。
【奨学金の連帯保証人の条件】
- 奨学生本人が未成年者の場合、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
- 奨学生本人が成年者の場合、その父母。父母がいない等の場合、奨学生本人のおじおば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- 返還誓約書に印字の誓約日時点で未成年者でないこと。
- 学生でないこと。
- 奨学生本人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- 債務整理中(破産等)でないこと。
- 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学生本人が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
2.については貸与予定総額の返還を条件に、貸与予定総額の2分の1以上の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者(年間収入金額、資産等の状況が以下の表のいずれかの基準を満たす者)に代えることができます。
連帯保証人は保証人と異なり、父母がいないなどの事情を除き、原則として父母を選定する必要があります。どうしても周りに依頼できる人がいない場合には、以下で解説するような代替手段を検討しましょう。
奨学金の保証人がいない場合の対処法・代替手段

保証人・連帯保証人の条件についてご紹介しましたが、奨学金の借入を検討されている方の中には保証人として選任できる人がいないという方もいるでしょう。
以下では、奨学金の保証人がいない場合の対処法を解説します。
【奨学金の保証人がいない場合の対処法・代替手段】
- 機関保証を利用する
- 学費保証を利用する
- 教育ローンを利用する
順に解説していきます。
機関保証を利用する
機関保証は、日本学生支援機構が指定する保証機関の連帯保証を受ける制度を指します。この制度を利用すると保証機関が奨学金の返済を保証し、奨学生が返済を延滞した場合には保証機関が代わりに返済を行います。
機関保証を利用するためには保証料が必要ですが、保証人を探す手間が省けるというメリットがあります。
学費保証を利用する
学費保証は、奨学金とは別に、学費の分割払いをサポートする制度です。学費を一括で支払うのが難しい場合、月々の支払いに分割することで、金銭的な負担を軽減できます。
専修学校や専門学校などでよく利用されるこの制度は、学生だけでなく保護者にとっても経済的な助けとなります。
また、学費保証の自動口座振替を利用することで、支払いの遅延や未払いを防ぐことができ、学校側にとっても安定した経営が可能になります。
教育ローンを利用する
教育ローンは、子どもの教育費を準備するために保護者が借入れを行う資金の準備方法です。
奨学金の保証人を用意することが難しい場合、教育ローンを利用することで、学費や生活費を賄うことができます。教育ローンは国の教育ローンと民間金融機関のローンに大別され、それぞれの条件や利率が異なります。
国の教育ローンは世帯年収の制限がありますが、民間の教育ローンは条件が比較的緩く、幅広い家庭が利用可能です。
まとめ
本記事では、奨学金の保証人条件や保証人がいない場合の代替手段を解説しました。
奨学金の保証人には厳しい条件があり、すべての人が保証人になれるわけではありません。
しかし、保証人が見つからない場合でも、機関保証や学費保証、教育ローンといった代替手段が存在します。
これから奨学金の利用を検討している方は、自分の状況に合った保証制度や代替手段を選び、学業に専念できる環境を整えましょう。
関連のInstagram投稿はこちら
Instagramでは、専門学生に役立つ情報を日々発信中!
興味がある人は是非いいねとフォローをお願いします!