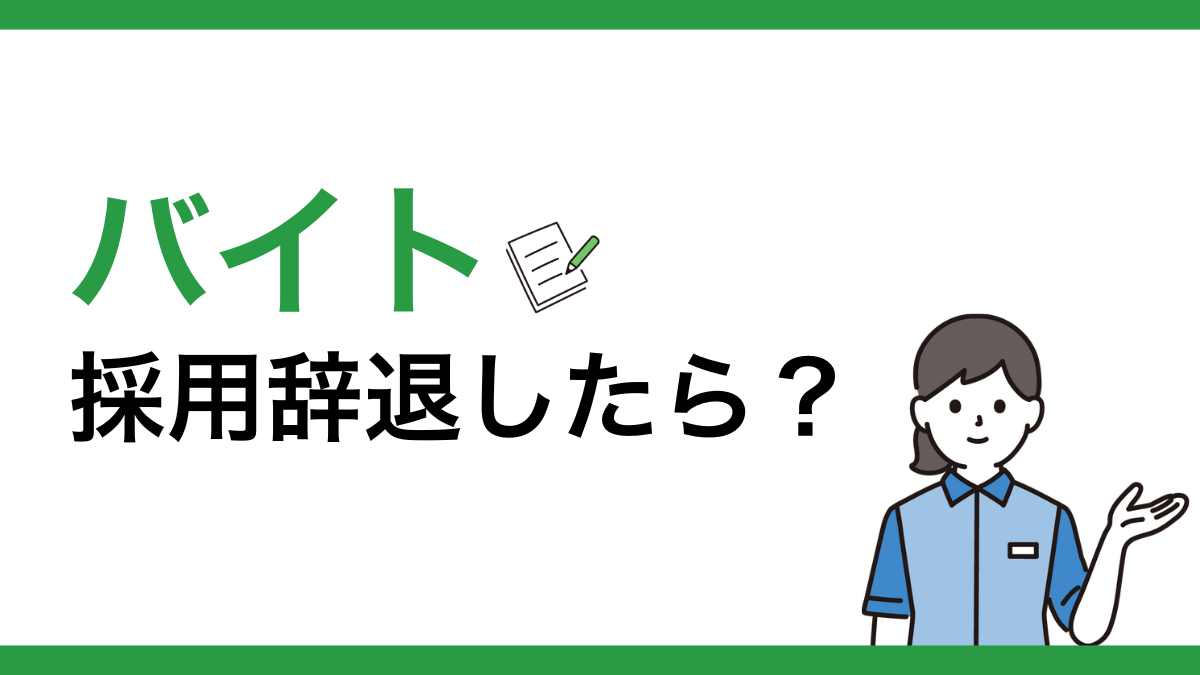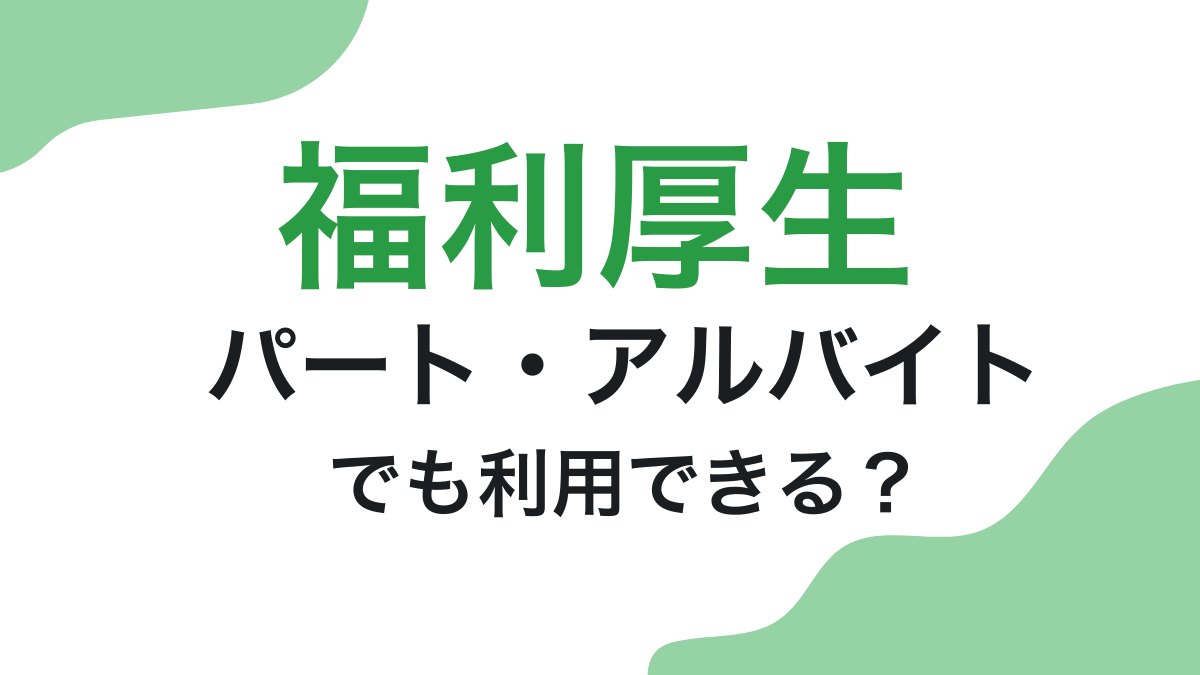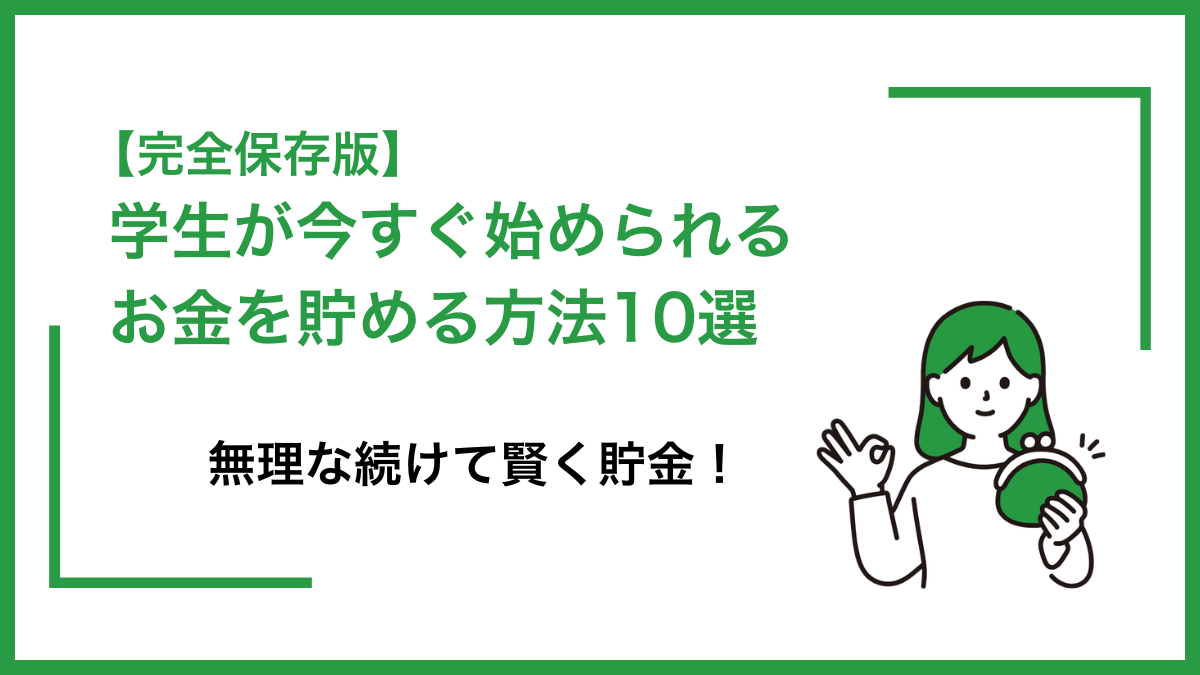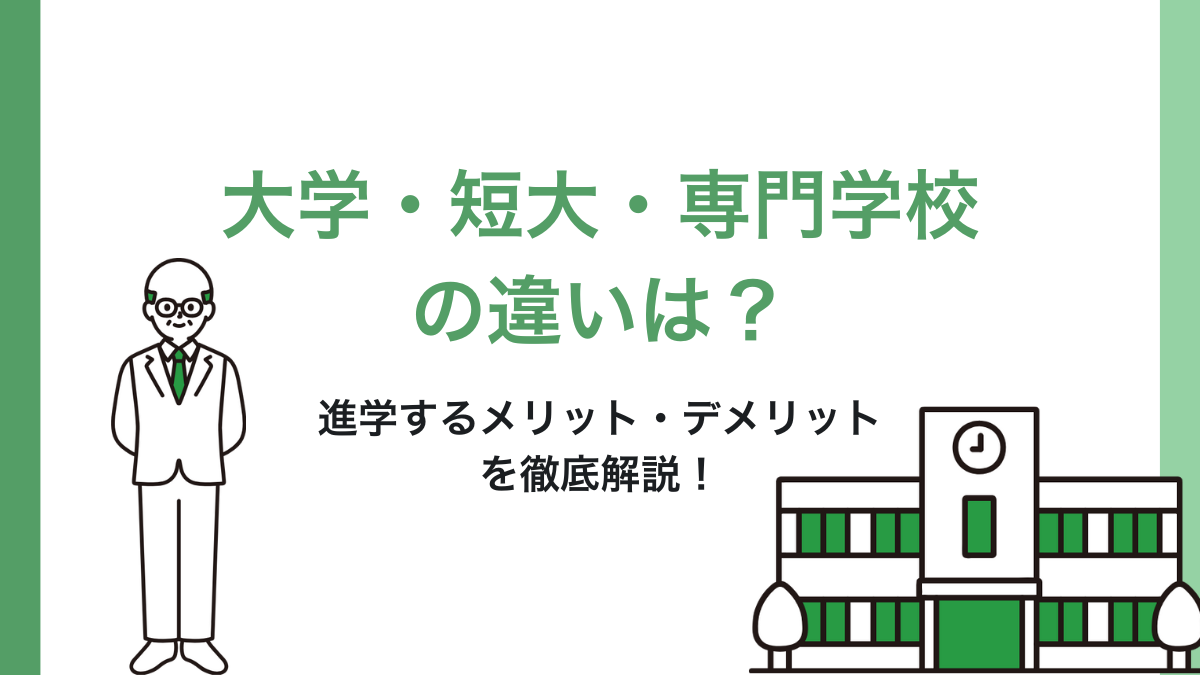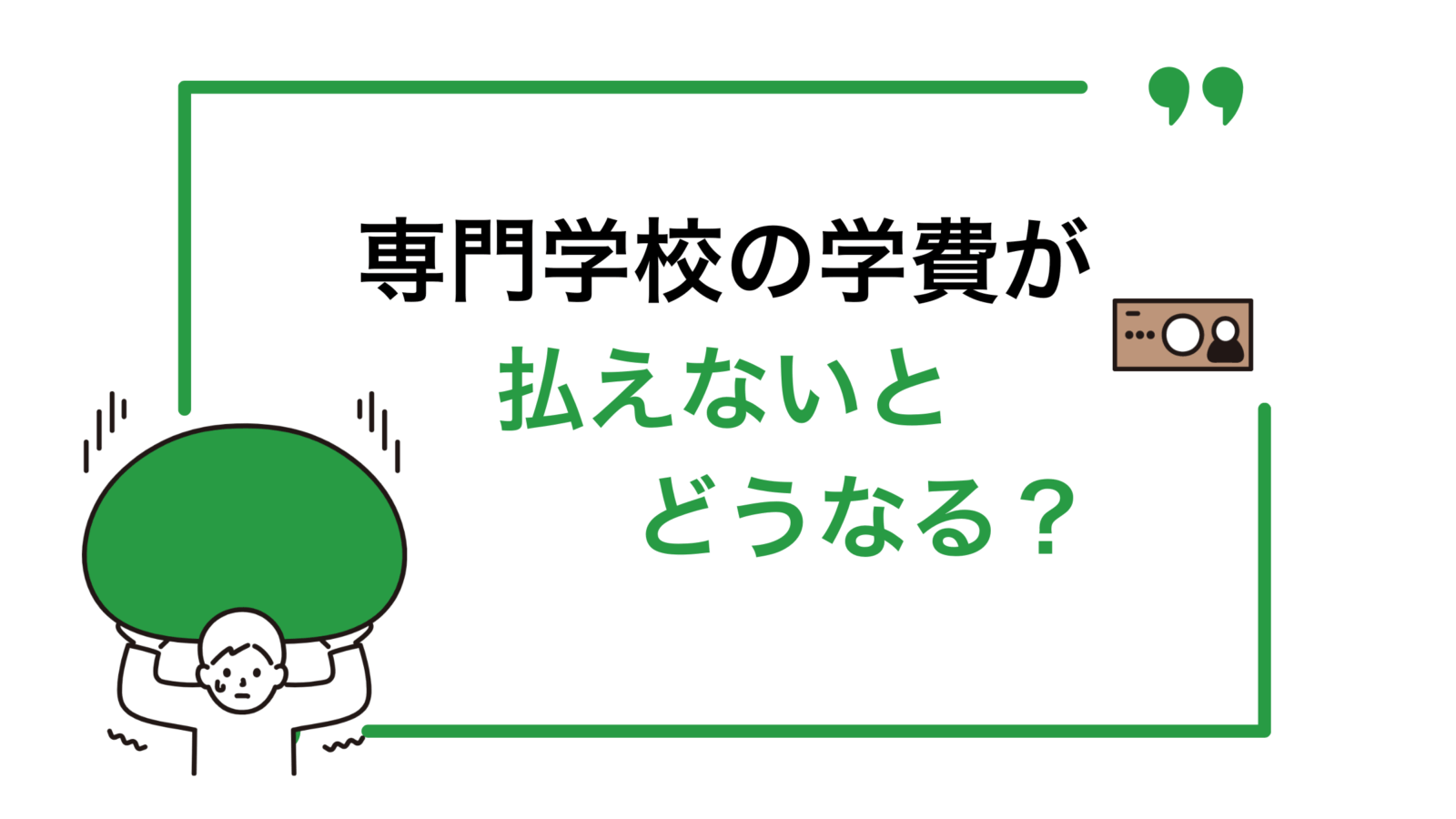大学進学を目指して浪人する方の中には、奨学金の申し込みができるのか不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、浪人生が申し込み可能な奨学金の種類や受け取り基準、申し込みの流れについて解説をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。
浪人生でも奨学金の申し込みは可能?

浪人生であっても奨学金の申し込みは可能です。
奨学金の目的は、経済的に進学が困難な学生を支援することにあるため、浪人生であっても奨学金を利用することができます。ただし浪人生が奨学金を利用するためには一定の条件を満たしている必要があります。また、それぞれ申し込む奨学金の種類によって申込み方法等が異なってくるため事前に確認をしておくことが必要です。
奨学金の種類

浪人生が申し込みできる奨学金には「貸与型奨学金」と「給付型奨学金」の大きく分けて2つの種類があります。
以下では、それぞれの概要や返済の有無などの特徴について解説します。
貸与型奨学金
貸与型奨学金とは、進学に必要な資金を貸与する形で支給される奨学金です。学生は卒業後に一定期間にわたって借りた金額を返済する必要があります。
貸与型には無利子で借りる「第一種奨学金」と、有利子で借りる「第二種奨学金」の2種類があります。
また、これらと併せて入学時の一時金として貸与する入学時特別増額貸与奨学金(利子付)があります。
給付型奨学金
給付型奨学金とは、返済の必要がない奨学金です。
日本学生支援機構の返済不要の給付型奨学金は、国費を財源として、優れた人にも関わらず経済的に困難な状況にある人に対して、進学を諦めることのないように進学を支援する制度です。
基本的に給付型のため返済は不要で、返済を保証するための保証人も不要となります。
上記より、各奨学金制度の特徴をまとめると以下のようになります。
| 奨学金の種類 | 返済の必要性 | 利子 | |
| 給付奨学金 | 返済不要 | ー | |
貸与奨学金 | 第一種奨学金 | 返済必要 | 利子なし |
| 第二種奨学金 | 利子あり | ||
| 入学時特別増額貸与奨学金 | |||
浪人生でも奨学金が申し込みできる条件とは

浪人生の奨学金の申し込み方法には「予約採用」と「在学採用」の2種類があり、それぞれの申込方法によって申込条件が異なります。
予約採用の申込条件
予約採用とは、学生が安心して進学できるように進学前に奨学金の利用について予約ができる制度です。
浪人生が予約採用で申し込む場合の条件は、「初めて高等学校等(本科)を卒業した年度の末日から申し込みを行う日までの期間が2年以内の人」とされています。また、高等専門学校の3年次終了後に大学等へ入学(編入学を除く)をする場合については、「3年次終了後2年以内の人」であれば申し込みが可能です。
参照元:浪人生でも申し込めますか。(2024年4月更新) | JASSO
在学採用の申込条件
在学採用とは、毎年春ごろに在籍する学校を通じて奨学金の申込みをすることができる制度です。
浪人生が在学採用で申し込む場合の条件は、以下1〜3のいずれかに該当する人となります。
1.高等学校等(※1)を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日(※2)までの期間が2年を経過していない人
※1高等学校等とは、国内の高等学校(本科)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のもの)を指します(インターナショナルスクールや在外教育施設等は含みません)。
※2現在在学する大学等に編入学又は転学した人は、編入学又は転学する前に在学していた学校に入学した日とします。なおこの場合、編入学又は転学する前に在学していた学校を卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する大学等に編入学又は転学している必要があります。
※3短期大学及び高等専門学校の専攻科は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認定を受けた専攻科に在籍している人に限り対象となります。また、本科卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する認定専攻科へ入学している必要があります。
※4ある専修学校専門課程を修了してから別の専門課程の学科へ入学した人は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から当該学科へ進学する日までの期間が2年を経過していない場合に限ります(ひとつめの専門課程で支給を受けていないことが前提です)。
※5大学等を一旦退学した人が別の大学等へ再入学した場合は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から別の大学等へ再入学するまでの期間が2年を経過していないことが必要となります。
2.高等学校卒業程度認定試験(以下「認定試験」といいます。)の受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない人(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含みます)で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
3.以下のA~Cのいずれかに該当する人(その他、外国の学校教育の課程を修了した人など)
A 学校教育法施行規則第150条に該当する高等学校等を卒業した人と同等以上の学力があると認められる以下のいずれかに該当する人であって、それに該当することとなった日の属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
(ア)外国において学校教育における12年の課程を修了した人又はこれに準ずる人で文部科学大臣の指定したもの
(イ)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した人
(ウ)文部科学大臣の指定した人
B 学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する人であって、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学しなくなった日の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
(ア)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(イ)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した人に準ずる学力があると認めたもの
C 学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する人であって、入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日までのもの
(ア)大学において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認めた人であって、18歳に達したもの
(イ)専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した人に準ずる学力があると認めた人であって、18歳に達したもの
引用元:進学後(在学採用)の給付奨学金の申込資格 | JASSO
奨学金の受給基準

また、予約採用と在学採用の申し込み時にはそれぞれ一定の学力基準を満たしていることや、生計維持者(原則父母)の経済状況、学修への意欲など要件が定められています。
ここでは一般的な基準である学力基準と家計基準について紹介します。
学力基準
奨学金の受け取り基準の1つとして学力基準が挙げられます。
せっかく奨学金を支給したとしても、その学生が意欲的に学習に取り組まなければその奨学金は意味のないものとなってしまいます。そのため、奨学金支給の判断材料として今までの学習成績を参考にされることが一般的です。
以下では予約採用と在学採用それぞれの学力基準について解説していきます。
予約採用の学力基準
予約採用の場合、申込時点で次の1.または2.のいずれかに該当する必要があります。
1.高等学校等における第1学年から申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること(評定平均における5段階評価をしていない学校は、これに準ずる学習成績)
2.将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、入学しようとする大学等における学修意欲を有することが、文書、面談等により確認できること。学修意欲等の確認は、高等学校等において面談の実施又はレポートの提出等により行う
参照元:進学前(予約採用)の給付奨学金の学力基準 | JASSO
在学採用の学力基準
在学採用の場合の学力基準は1年次の場合、以下の1.~3.のいずれかに該当することが基準となります。
- 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、または、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
- 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
- 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
また、2年次以降の場合、次の1、2のいずれかに該当することが基準となります。
- GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
- 修得した単位数が標準単位数以上であり、将来社会で自立し活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
このように、奨学金の学力基準には一定の学力の成績と学修への意欲が求められます。
実際に奨学金の申込みする際に学力基準に達していなかったといったことがないように、必要な学力基準についてはあらかじめ把握することが重要です。
参照元:進学後(在学採用)の給付奨学金の学力基準 | JASSO
家計基準
奨学金のもうひとつの受け取り基準として家計基準が挙げられます。
家計基準には、収入基準と資産基準の2つの基準があり、申込者本人と生計維持者が、これら2つの基準のいずれにも該当する必要があります。父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となります。
収入基準については、貸与型奨学金と給付型奨学金で基準が異なります。詳しい基準については以下で説明します。
貸与型奨学金の収入基準
貸与型奨学金の収入基準については、住民税情報により算出された貸与額算定基準額 が下記表に該当するか審査が行われます。
大学や短期大学、専修学校(専門過程)に進学される場合の基準は以下のとおりです。
| 希望する奨学金 | 家計基準 |
| 第一種・第二種奨学金の併用付与 | 生計維持者の付与額算定基準額が164,600円以下であること |
| 第一種奨学金 | 生計維持者の付与額算定基準額が189,400円以下であること |
| 第二種奨学金 | 生計維持者の付与額算定基準額が381,500円以下であること |
貸与額算定基準額の計算方法は以下のとおりです。
| 貸与額算定基準額(a) =(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(b) -(多子控除)(c)-(ひとり親控除)(d) -(私立自宅外控除)(e) (100円未満は切り捨て) (a)市町村民税所得割が非課税の人は、 この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。(b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。(c)生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。 扶養している子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい人数を適用します。(例)生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、(3-2)人 ×40,000円=40,000円となります。(d)ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。(e)在学採用の審査において、あなたが私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場合に22,000円を控除します。予約採用の審査においては一律0円となります。 |
貸与額算定基準額(a) =(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(b) -(多子控除)(c)-(ひとり親控除)(d) -(私立自宅外控除)(e) (100円未満は切り捨て)
(a)市町村民税所得割が非課税の人は、 この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。
(b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
(c)生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。 扶養している子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい人数を適用します。
(例)生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、(3-2)人 ×40,000円=40,000円となります。
(d)ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。
(e)在学採用の審査において、あなたが私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場合に22,000円を控除します。予約採用の審査においては一律0円となります。
参照元:進学前(予約採用)の第一種奨学金の家計基準 | JASSO
給付型奨学金の収入基準
給付型奨学金の収入基準は給付奨学生と生計維持者の住民税の情報を利用し日本学生支援機構が支給額算定基準額を計算することで判定を行っており、その金額に応じて支援区分を「第1区分」〜「第4区分」まで区分されます。
第1区分が奨学金の支給金額が最も多く、同じ第1区分であっても、進学する大学が公立であるか私立であるか、自宅通学かそうでないかなどによって受給できる金額が変わってきます。
給付型奨学金の収入基準の目安については以下の表のとおりです。
| 支援区分 | 収入基準 |
第1区分 | 給付奨学生と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること具体的には給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額が100円未満 |
第2区分 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
第3区分 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
第4区分 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であること |
支給額算定基準額についてはご自身で確認することが可能です。具体的な基準額を確認されたい方は、課税証明書やマイナポータルによる情報開示で住民税の情報を確認した上で日本学生支援機構のHP記載の「支給額算定基準額の計算手順」に沿って算出をすることが可能です。
参照元:進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準 | JASSO
参照元:進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準 | JASSO
資産基準
資産基準は、申込日時点の申込者と生計維持者(2人)の資産額の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であることが条件となっています。
ここでいう資産額とは、現金やこれに準ずるもの(退職金含む。投資信託、投資資産として保有する金・銀等)や預貯金(普通預金、定期預金)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)が該当します。
土地、建物等の不動産や満期、解約前の保険の掛け金、住宅ローン等の負債との相殺、貯蓄型生命保険や学資保険などは資産の対象とはならないので注意しましょう。
参照元:進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準 | JASSO
参照元:進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準 | JASSO
浪人生の奨学金申し込みの流れについて解説
これまでは奨学金の申込条件について解説をしましたが、実際に奨学金申し込みをするためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
ここからは予約採用と在学採用それぞれの奨学金の申し込み手続きの流れについて説明していきます。
予約採用の場合
予約採用の場合の奨学金の申込みは、学校を通じて行います。浪人生で既に学校を卒業している場合についても、在籍していた高校を通しての受付となります。ただし、高等学校卒業程度認定試験合格者(合格見込者を含む)の予約採用については、日本学生支援機構への直接申込みとなります。
進学前の手続きについては、まず高校で申し込み関係書類を受け取った後、インターネットより申込情報の入力をし申し込みを行います。学校から受け取ったIDとパスワードを使って「スカラネット」という奨学金申込専用ホームページより必要事項を入力し申し込み手続きを行います。
次にマイナンバーを日本学生支援機構宛てに簡易書留で郵送します。
申込関係書類に同封の「マイナンバー提出書のセット」の専用封筒を使い、必要な書類を郵便局の窓口から簡易書留で郵送します。この際に学校に提出しないよう注意してください。
また、高校への申込書類の提出も必要です。必要書類については、申込関係書類に記載されている内容をよく確認し、漏れのないよう作成しましょう。申し込み手続き完了後、採用候補者の選考結果については奨学金を申し込んだ学校を通じて通知されます。
進学後には、進学先の学校に「採用候補者決定通知【進学先提出用】」の提出を行います。また、進学先より必要な進学届入力下書き用紙」と「識別番号(ユーザIDとパスワード)を受取り、進学先の学校が指定する期間までにスカラネットより「進学届」を提出します。
その後、最後に日本学生支援機構より「識別番号(ユーザIDとパスワード)」が付与されたら、「進学届」を日本学生支援機構へ提出します。その後、奨学生としての採用・通知が届き、奨学金の振り込みが開始されます。
このように予約採用は申し込み開始から完了までには時間がかかるため、計画的に準備を進めるようにしましょう。
在学採用の場合
在学採用の場合は在学中の学校を通して申し込みを行います。
まず、在学中の学校から申込みに必要なユーザIDとパスワードを受け取り、学校が定める入力期限までにスカラネットでの申込みを行います。
書類を在学中の学校で受け取った後は予約採用と同様に日本学生支援機構宛てにマイナンバーの提出を行います。
申込手続き後に在籍する学校が申込者の学業成績・学修意欲を確認し、日本学生支援機構に推薦を行うという流れとなり、結果については進学先の学校より連絡がされます。
その後の手続きや書類の提出期限については在学中の学校の指示に従って進めるようにしましょう。
まとめ
本記事では、浪人生が申し込み可能な奨学金やその条件、申し込みの流れについて解説しました。
浪人生でも奨学金を利用することは可能ですが、利用するためにはさまざまな条件を満たしている必要があります。奨学金の利用を検討する際には各制度の概要や諸条件について前もって把握し、スムーズに申し込みが完了できるようにしましょう。
関連のInstagram投稿はこちら
Instagramでは、専門学生に役立つ情報を日々発信中!
興味がある人は是非いいねとフォローをお願いします!