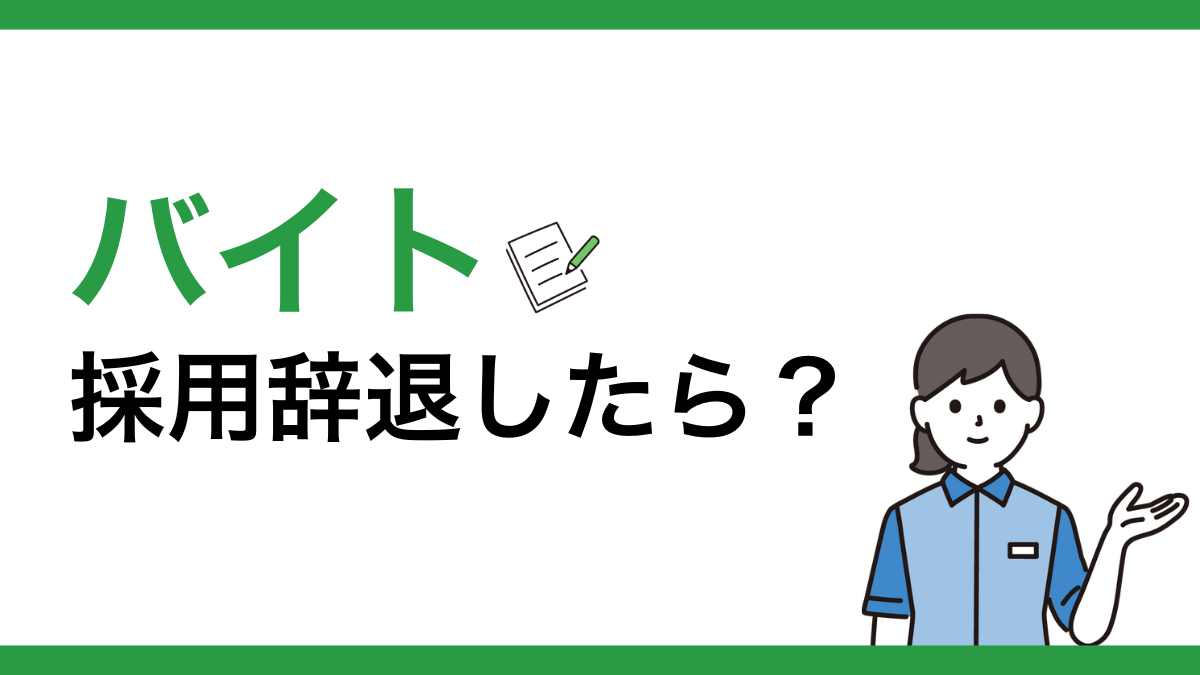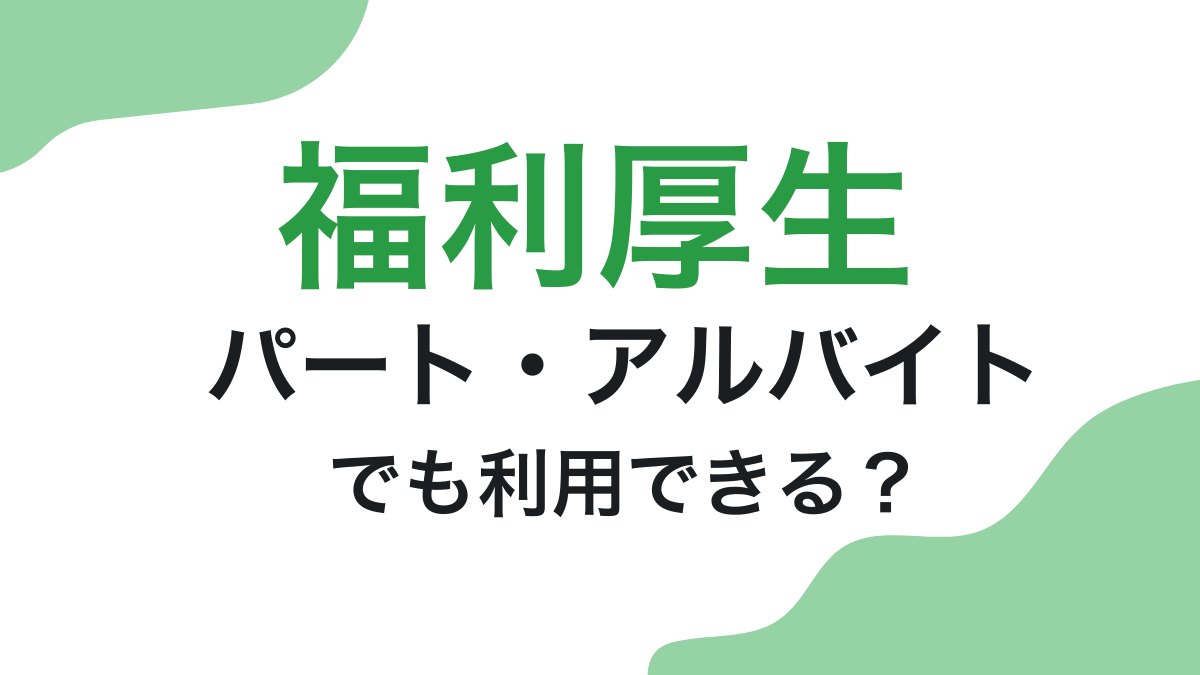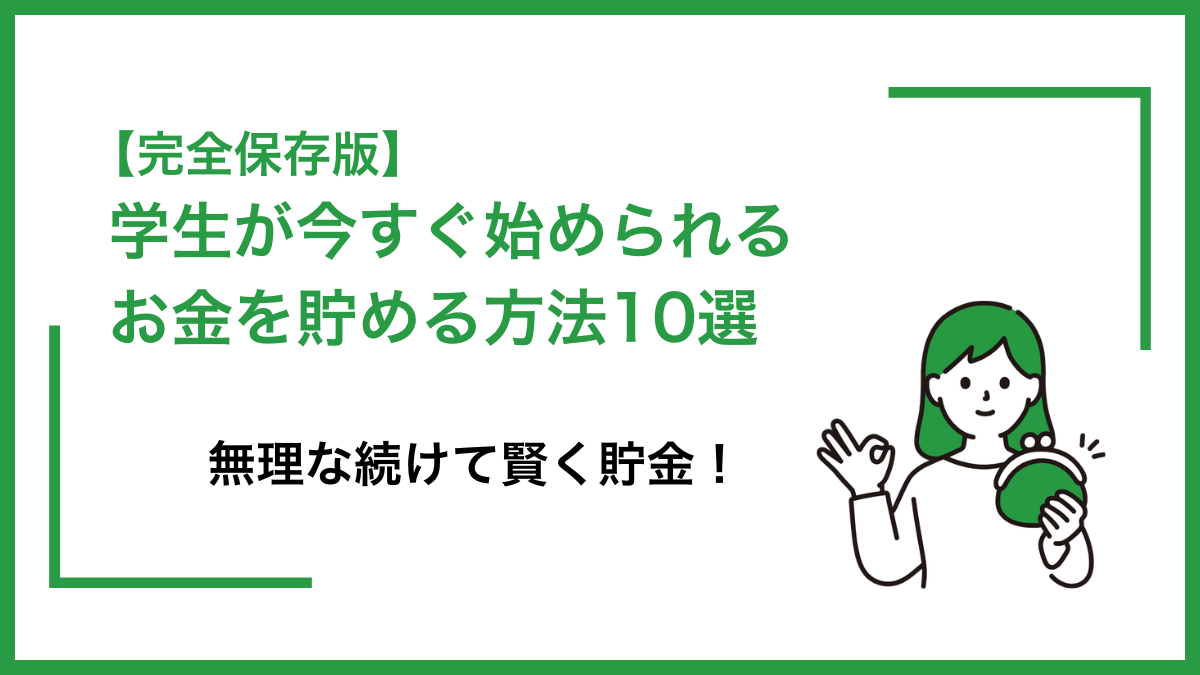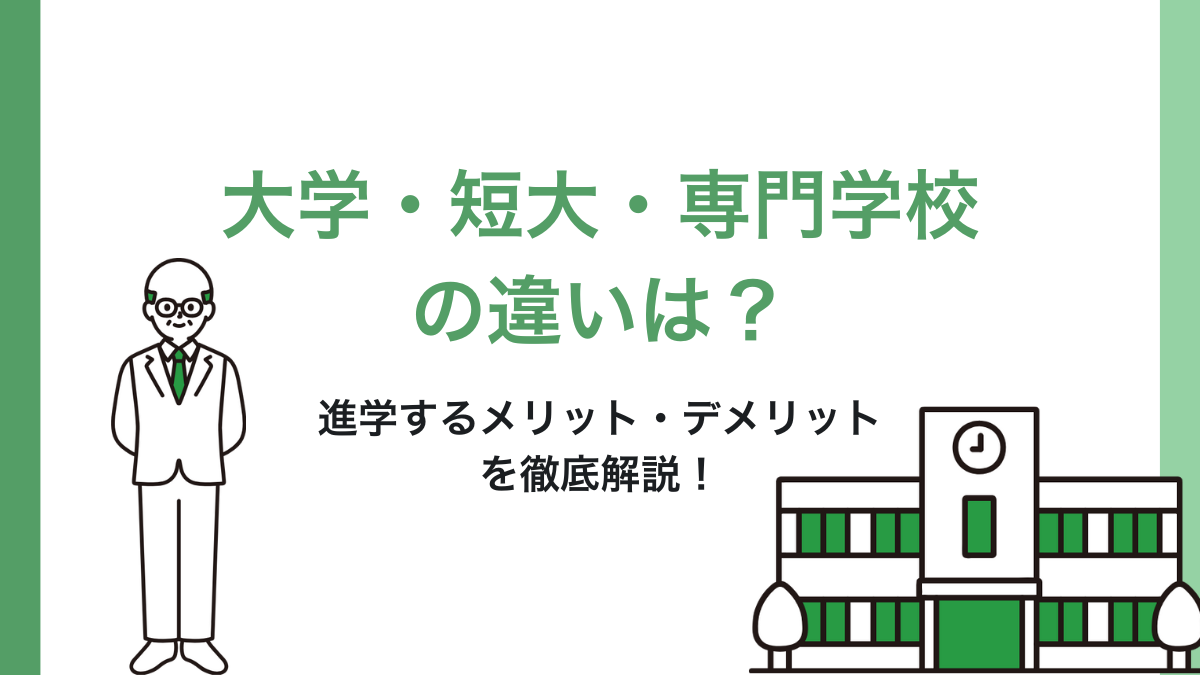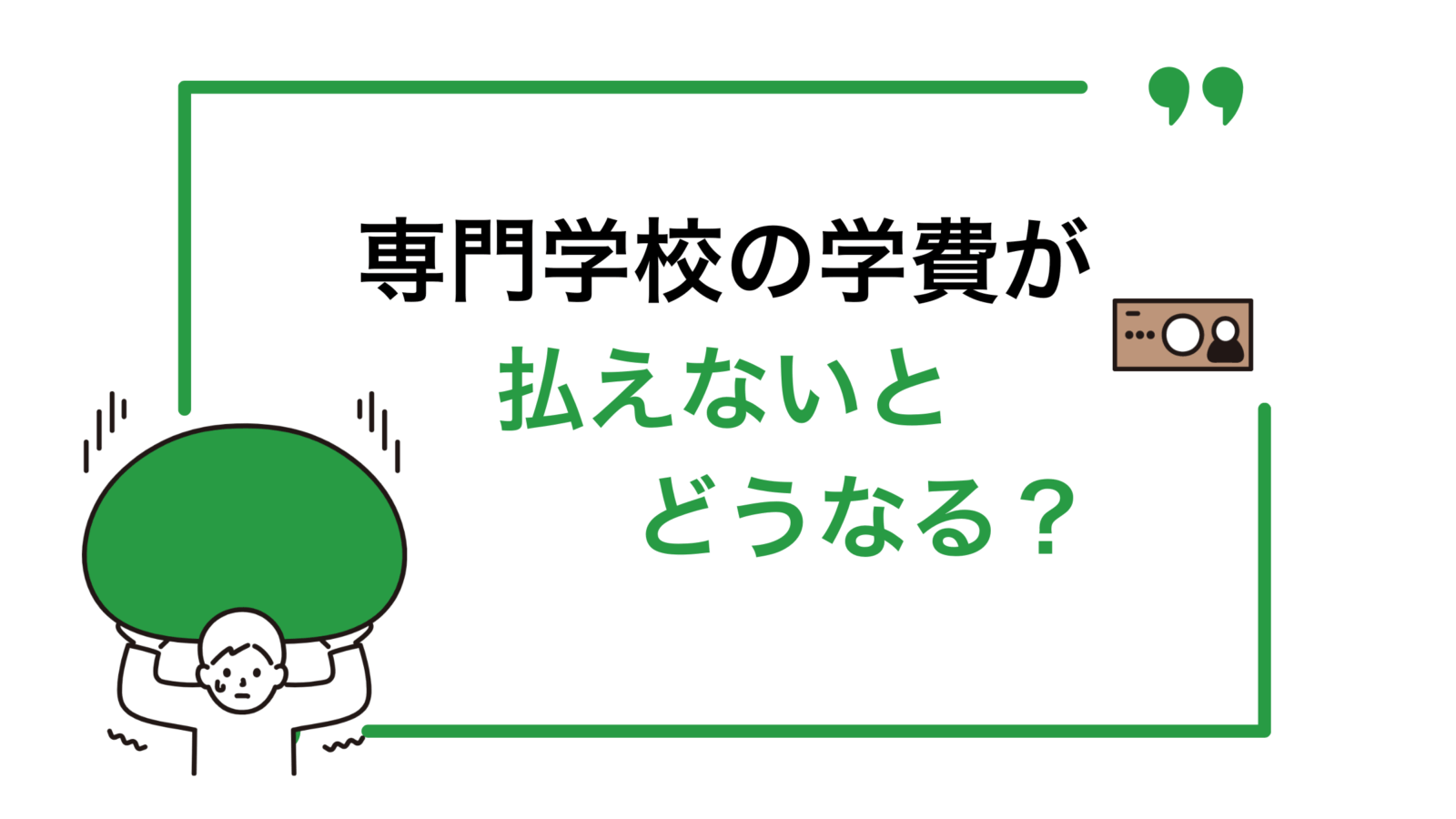奨学金の申請時に直面する大きな課題のひとつが、保証人の確保です。しかし、適切な保証人が見つからない場合でも、諦める必要はありません。
この記事では、奨学金の保証人制度について解説し、保証人が見つからない場合の具体的な対処法をご紹介します。
奨学金の「保証人」「連帯保証人」とは

日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けるにあたって、「連帯保証人」や「保証人」が返還を保証する人的保証制度があります。
連帯保証人・保証人ともに奨学金の返還が延滞した場合に、奨学生に代わって返還する義務がありますが、それぞれにはどのような違いがあるのでしょうか。
以下に、それぞれの違いをまとめます。
| 連帯保証人 | 保証人 | |
| 分別の利益 | 【なし】保証人の数に関わらず、奨学生に代わって全額返済する | 【あり】保証人の数で割った金額のみ返済すれば良い |
| 催告の抗弁権 | 【なし】奨学生に請求するよう主張することなどは認められていない | 【あり】奨学生が返済できなかった場合、まずは奨学生に請求するよう主張できる |
| 検索の抗弁権 | 【なし】奨学生の財産の強制執行などは主張できない | 【あり】奨学生が返済できなくなった場合、財産に強制執行して残額回収するよう主張できる |
上記のとおり、連帯保証人は保証人に比べて返済額や返済義務への主張の観点で、責任が重いと言えるでしょう。
連帯保証人の選任条件とは
連帯保証人は奨学生本人と連帯して返還の責任を負う人であり、原則として「父母」を選任することとなっています。
日本学生支援機構では、連帯保証人の選任条件は以下のように記載されています。
- (1)あなた(奨学生本人)が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること。
- (2)あなた(奨学生本人)が成年者の場合は、その父母。父母がいない等の場合は、あなた(奨学生本人)の兄弟姉妹・おじ・おば等の4親等以内の親族であること。
- (3)未成年者および学生でないこと。
- (4)あなた(奨学生本人)の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- (5)債務整理中(破産等)でないこと。
- (6)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
- 連帯保証人に「4親等以内の成年親族」でない人を選任する場合は、下記の基準・条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてください。「返還誓約書」提出時に印鑑登録証明書等の書類に加えて「返還保証書」および基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書の提出が必要です。
- 「返還を確実に保証できる人」とは、以下(a)~(c)いずれかの基準に該当し、書類を提出できる人です。
- (a)源泉徴収票、確定申告書(控)、所得証明書、年金振込通知書等(※1)
・給与所得者の場合:年間収入≧320万円
・給与所得者以外の場合:[給与所得以外+給与所得の方も含む]年間所得≧220万円
(※1 年金収入は給与として扱う)- (b)預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等
預金残高+評価額≧貸与予定総額- (c)(a)と(b)の組み合わせ
(預金残高+評価額)/16年+年間収入≧320万円(※2)
(※2 所得の場合は220万円)
保証人の選任条件とは
保証人は、奨学生と連帯保証人が返還できない場合に奨学生に代わって返還する人を指します。保証人は原則として「おじ・おば・兄弟姉妹等」を選任することとなっています。
日本学生支援機構では、連帯保証人の選任条件は以下のように記載されています。
- (1)あなた(奨学生本人)および連帯保証人と別生計であること。
- (2)あなた(奨学生本人)の父母を除く、おじ・おば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であること。
- (3)返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日現在で65歳未満であること。
- (4)未成年者および学生でないこと。
- (5)あなた(奨学生本人)または連帯保証人の配偶者(婚約者を含む)でないこと。
- (6)債務整理中(破産等)でないこと。
- (7)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満45歳を超える場合、その時点で60歳未満であること。
- 保証人に、「4親等以内の成年親族」でない人、または65歳以上の人のいずれか(または両方)に該当する人を選任する場合は、奨学生本人及び連帯保証人と別生計で下記の基準・条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてください。「返還誓約書」提出時に印鑑登録証明書等の書類に加えて「返還保証書」および基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書の提出が必要です。
- 必ず事前に、基準を満たしていることを収入・所得や資産に関する証明書により確認してください。「返還保証書」を提出することができない場合や、基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書を提出することができない場合は、「別人物を選任する」か「機関保証制度」を選択してください。
- 「返還を確実に保証できる人」とは、以下(a)~(c)いずれかの基準に該当し、書類を提出できる人です。
- (a)源泉徴収票、確定申告書(控)、所得証明書、年金振込通知書等(※1)
・給与所得者の場合:年間収入≧320万円
・給与所得者以外の場合:[給与所得以外+給与所得の方も含む]年間所得≧220万円
(※1 年金収入は給与として扱う)- (b)預貯金残高証明書、 固定資産評価証明書等
預金残高+評価額≧貸与予定総額(返還残額)の2分の1- (c)(a)と(b)の組み合わせ
(預金残高+評価額)/16年+年間収入≧320万円(※2)
(※2 所得の場合は220万円)
奨学金の保証人を依頼できる人がいない場合の対処法

前述した連帯保証人・保証人の選任条件に合致する人が見つからない場合でも、進学に伴う学費の支払いを諦める必要はありません。日本学生支援機構には人的保証以外にも保証制度が用意されている他、代替手段もあります。
今回ご紹介する奨学金の保証人を依頼できる人がいない場合の対処法は以下のとおりです。
【奨学金の保証人を依頼できる人がいない場合の対処法】
- 機関保証制度を利用する
- 返済不要の給付型奨学金を利用する
- 代替手段として教育ローンを利用する
以下でそれぞれについて詳しく解説します。
機関保証制度を利用する
機関保証制度とは、日本学生支援機構の奨学金を利用するにあたって、奨学生が一定の保証料を支払うことで日本学生支援機構が指定する保証機関が連帯保証する制度を指します。機関保証を利用すると、個人に保証人を依頼する必要がなくなり、保証人が見つからない学生でも奨学金を申し込めるのがメリットでしょう。
ただし、保証期間に保証料を支払わなければならないため、負担額は増えてしまうのがデメリットと言えます。
また、奨学生が一定期間延滞した場合には、奨学生に代わって保証機関が日本学生支援機構に返済します。その後、保証機関が奨学生に返済額を一括請求するという流れになります。
参照元:保証制度について | JASSO
返済不要の給付型奨学金を利用する
日本学生支援機構の返済不要の給付型奨学金は、国費を財源として、優れた人にも関わらず経済的に困難な状況にある人に対して、進学を諦めることのないように進学を支援する制度です。
基本的に給付型のため返済は不要で、返済を保証するための保証人も不要となります。
給付型奨学金は日本学生支援機構以外にもさまざまな運営元があります。
【給付型奨学金の主な種類】
- 日本学生支援機構の給付型奨学金
- 各大学・専門学校給付型奨学金
- 地方自治体が提供する給付型奨学金
- 民間団体や企業が提供する給付型奨学金
申し込みに際しては、各奨学金制度の募集要項を十分に確認し、必要書類を揃えて期限内に申請することが重要です。
代替手段として教育ローンを利用する
教育ローンは、奨学金の代替または補完策として考えられる選択肢の一つです。奨学金の保証人が見つからない場合や、奨学金だけでは資金が足りない場合に検討すると良いでしょう。
教育ローンは日本政策金融公庫や銀行や信用金庫などの民間金融機関などが提供しています。
提供元によって金利や借入期間、借入上限額などの諸条件は異なるため、自身の状況に合わせて選択をしましょう。
まとめ
本記事では、奨学金の保証人・連帯保証人の違いや保証人が見つからない場合の対処方法などを解説しました。
奨学金の人的保証制度を利用する場合、連帯保証人・保証人には選任条件があります。申し込みをする前には保証人を依頼できる人がいるのかを確認し、万が一保証人を依頼できない場合には別の保証制度や代替手段を検討しましょう。
関連のInstagram投稿はこちら
Instagramでは、専門学生に役立つ情報を日々発信中!
興味がある人は是非いいねとフォローをお願いします!